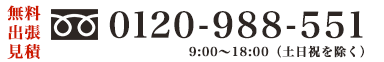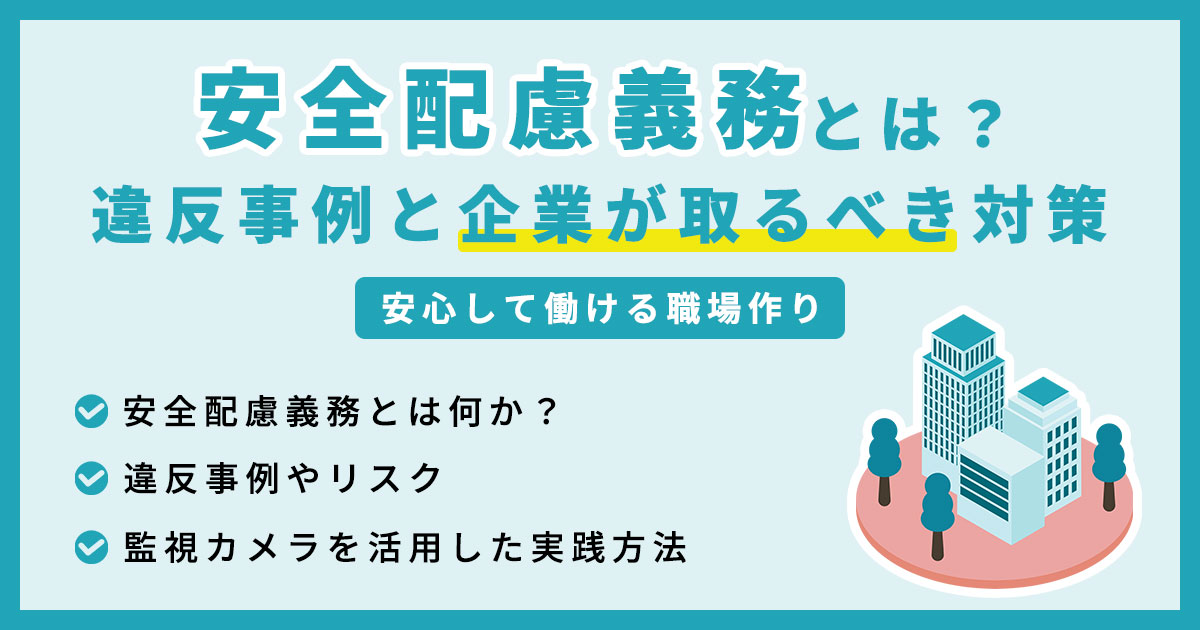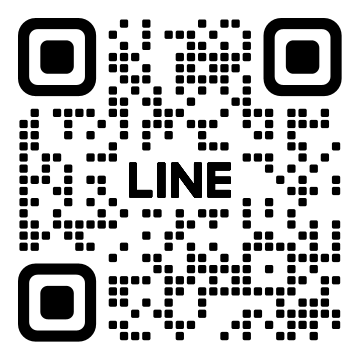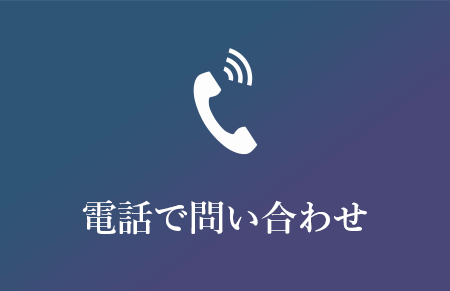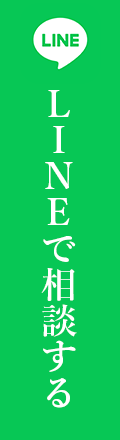安全配慮義務とは何かわかりやすく解説!
違反事例と企業が取るべき対策
「法律で決められた義務は守っているつもりだけど、これで本当に十分なんだろうか」
そんな不安を感じたことはありませんか?
実際には、労働時間の管理不足やハラスメントの見過ごし、健康診断の未実施といった小さな対応漏れが、大きな事故や損害賠償につながるケースがあります。
そこで重要になるのが、企業に課せられた「安全配慮義務」です。
社員が安全かつ健康に働けるよう配慮する義務であり、違反すれば法的責任や企業イメージの悪化を招く可能性があります。
本記事では、安全配慮義務の基本から違反事例、そして具体的な対策までをわかりやすく解説します。
この記事でわかること
- 安全配慮義務とは何か
- 違反事例とそのリスク
- 企業が実施すべき具体的な対策
- 監視カメラを活用した実践方法
社員が安心して働ける職場をつくりたい方、法的リスクを避けたい経営者・人事担当者の方は、ぜひ参考にしてください。
安全配慮義務とは?
社員が安心して働ける環境を整えることは、企業の責任です。
ここでは安全配慮義務の定義や対象範囲、注意義務との違いを理解していきましょう。
ここで解説すること
- 安全配慮義務の定義
- 対象者・対象行為・義務の範囲
- 注意義務との違い
安全配慮義務の定義

安全配慮義務とは、労働者が安全かつ健康に働けるように企業が必要な配慮を行う義務を指します。
労働契約法第5条によると「使用者は、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働できるよう配慮する義務を負う」と明記されており、企業の責任は法律上明確です。
出典:法令検索e-GOV「労働契約法第五条」たとえば以下のような行為が安全配慮義務に含まれます。
- 職場の安全設備を整える
- 長時間労働を防ぐ
- パワハラ・セクハラ防止体制をつくる
- 健康診断やストレスチェックを実施する
このように、安全配慮義務は社員を守るために日常的に取り組むべき企業責任です。
対象者・対象行為・義務の範囲

安全配慮義務の対象は、すべての労働者と、その業務に関連する行為です。
企業は社員の生命や健康を守るために、広い範囲で配慮する責任があります。
具体的な範囲は次のとおりです。
- 正社員・契約社員・パート・派遣社員も含む
- 業務時間中の事故防止や健康管理
- ハラスメント防止や相談窓口の設置
- 安全設備や労働環境の整備
正社員だけ守ればいいわけではなく、働くすべての人に対して、安全に働けるように責任を果たす必要があるのです。
注意義務との違い
よく比較される注意義務との違いを見ておきましょう。
注意義務は「一般的に気をつけるべき義務」です。
一方で安全配慮義務は「労働者の安全と健康を守ること」に特化しています。
違いを整理すると下表のようになります。
| 義務の種類 | 内容 | 適用範囲 |
|---|---|---|
| 注意義務 | 一般的に相手へ損害を与えないよう注意する義務 | 社会生活や契約全般 |
| 安全配慮義務 | 労働者の命や健康を守るための措置を取る義務 | 労働契約に基づく職場環境 |
安全配慮義務は注意義務の一部にあたり、働く人の安全確保に焦点を当てたものと理解するとわかりやすいでしょう。
安全配慮義務に違反した場合のリスクと罰則
安全配慮義務に違反したからといって、直ちに刑事罰が科されるわけではありません。
しかし、放置すれば企業は別の法律違反や損害賠償責任を負う可能性があり、社会的信用を失う危険があります。
ここでは、法律面・経営面のリスクを整理していきましょう。
ここで解説すること
- 直接的な罰則は労働契約法にはない
- 違反した場合は別のトラブルが発生する可能性がある
- 企業イメージの毀損や離職リスクにつながる
直接的な罰則は労働契約法にはない
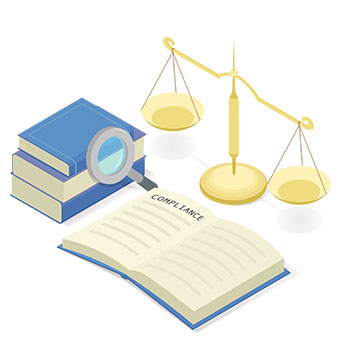
労働契約法そのものには、安全配慮義務違反に対して直接の罰則は定められていません。
労働契約法は「労働者を守るための基本ルール」を示す法律です。
罰則を科すのではなく、裁判で損害賠償責任を問う際の根拠として使われます。
たとえば企業が安全配慮義務を怠った場合には、次のようなリスクが生じます。
- 労働者が病気やけがを負った場合、損害賠償を請求される
- ハラスメントを放置すれば使用者責任を問われる
- 長時間労働を放置した結果、過労死で企業が損害賠償を命じられた事例もある
労働契約法には直接的な処罰規定はありません。
ただし、違反すれば民事上の責任を問われ、結果的に企業へ損害を与える可能性が高いです。
違反した場合は別のトラブルが発生する可能性がある

安全配慮義務そのものに罰則はなくても、違反を放置すれば他の法律違反や裁判に発展する可能性があります。
労働者の生命や健康を守る対策をしなかった場合、労働安全衛生法など別の法律が適用され、企業は罰金や行政処分を受けるケースもあります。
さらに損害賠償請求につながるリスクも高いです。
実際に起こり得るトラブルは次のとおりです。
- 労働安全衛生法違反として50万円以下の罰金
- 長時間労働による過労死で損害賠償を命じられる
- ハラスメント放置で使用者責任を問われる
直接の罰則はなくても、安全配慮義務を怠ると別の形で企業に重い責任が降りかかります。
企業イメージの毀損や離職リスクにつながる

安全配慮義務を怠ると、企業の評判低下や人材流出などの経営リスクにも直結します。
社員が安心して働けない職場だと、内部の不満がSNSや口コミで広まりやすいためです。
また、既存社員が「ここでは働き続けられない」と感じて離職率が上がり、人材確保が難しくなります。
考えられる影響は次のとおりです。
- 「ブラック企業」と評判が広まる
- 優秀な人材が集まらず採用コストが上がる
- 社員の離職率が上がり、現場がさらに疲弊する
安全配慮義務違反は企業の信頼を落とし、安定した経営ができなくなります。
安全配慮義務違反の代表的な事例
安全配慮義務違反は、特定の業種や職場だけでなく、あらゆる現場で起こり得ます。
ここでは代表的な違反事例を紹介します。
紹介する違反事例
- 学校における安全配慮義務違反の事例
- 介護施設における安全配慮義務違反の事例
- パワハラを見過ごした場合
- メンタル不調への未対応による損害賠償
学校における安全配慮義務違反の事例

学校における安全配慮義務違反は、部活動や授業、学校生活で生徒の安全を守れなかった場合に発生します。
学校で実際に問題となるのは次のような事例です。
- 部活動での熱中症や事故を放置した
- 校舎や施設の不備で転倒事故が発生した
- いじめを知りながら放置した結果、生徒の心身に被害が及んだ
学校は教育だけでなく「安全を守る責任」も担っており、対応を怠ると法的責任や社会的批判に直結してしまいます。
介護施設における安全配慮義務違反の事例

介護施設における安全配慮義務違反は、利用者の命や健康を守る体制を整えなかった場合です。
高齢者や要介護者は体力や判断力が弱く、転倒や誤嚥などのリスクが高いため、施設では高い安全配慮が求められています。
これを怠ると、重大事故や虐待につながり、損害賠償責任を問われる事態になりかねません。
実際に問題となる事例は以下のとおりです。
- 転倒を防ぐ環境整備を怠った結果の骨折
- 職員の不注意による薬の取り違え
- 食事中の誤嚥事故を見過ごした
- 職員による虐待を放置した
日常的な安全管理と職員教育を徹底しないと、施設の信頼そのものを失う危険があります。
オフィスのパワハラを見過ごした場合

職場でパワハラを放置すると、安全配慮義務違反にあたる可能性が高く、企業は法的責任を負うことになります。
見過ごした場合に考えられるリスクは次のとおりです。
- 精神疾患の発症により労災認定される
- 損害賠償請求を受け、企業に多額の負担が発生する
- 社内での不信感が広がり、離職率が上がる
このようにパワハラの軽視は、企業の信頼や存続にかかわる問題となり得ます。
メンタル不調への未対応による損害賠償

社員のメンタル不調に適切に対応しなかった場合も、安全配慮義務違反として企業が損害賠償責任を負う可能性があります。
うつ病や適応障害などの精神疾患は、長時間労働や職場環境の悪化が原因となることが少なくありません。
- 長時間労働を放置した結果、うつ病を発症
- 精神疾患を抱えた社員を配置転換せず業務を続けさせた
- 相談窓口を設けず、休職や復職のサポートを行わなかった
企業がその兆候を把握しながら放置した場合、従業員を守る配慮を怠ったと判断されるでしょう。
メンタル面のケアを怠れば、法的責任や損害賠償に発展し、企業に打撃があります。
企業が取るべき安全配慮義務の具体的対策
安全配慮義務を果たすには、知識として理解するだけでは十分ではありません。
実際に職場環境へ落とし込み、従業員が安心して働ける仕組みを整えることが必要です。
ここでは企業が取り組むべき具体的な対策を整理しました。
安全配慮義務の具体的対策
- ハラスメント防止と教育の強化
- 健康診断・ストレスチェックの実施
- 労働時間と休憩管理の徹底
- 産業医やカウンセラーの設置
- 相談窓口・通報制度の整備
- 就業環境の整備(空調・安全設備など)
- 監視カメラやセンサーの導入による見守り体制
ハラスメント防止と教育の強化
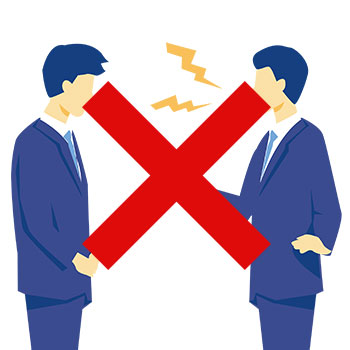
企業が安全配慮義務を果たすためには、パワハラやセクハラを未然に防ぐ取り組みと、従業員への教育が必要不可欠です。
有効な取り組みには次のようなものがあります。
- 就業規則にハラスメント禁止を明記する
- 研修やeラーニングで全社員に教育を行う
- 管理職向けにケーススタディを実施する
- 相談窓口を周知し、安心して利用できる体制を整える
ハラスメント防止を組織全体の習慣として定着させれば、安全配慮義務に自然と対応できます。
健康診断・ストレスチェックの実施
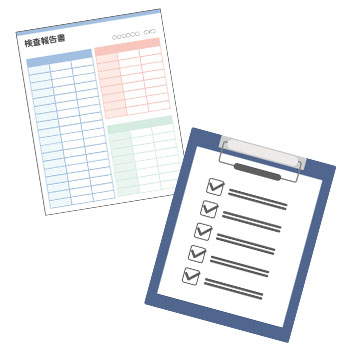
企業は定期的な健康診断やストレスチェックを実施し、従業員の心身の状態を把握することが重要です。
病気やメンタルの不調は、早期に発見すれば大きな問題になる前に対応できます。
一方で怠ると、安全配慮義務違反として損害賠償請求を受ける可能性もあるのです。
取り組むべき内容には次のようなものがあります。
- 年1回以上の定期健康診断を実施する
- 高ストレス者に面談やフォローを行う
- 結果を分析し、職場環境の改善につなげる
- 産業医やカウンセラーと連携して対応する
このように、健康診断やストレスチェックなど、従業員を守るための取り組みが大切です。
労働時間と休憩管理の徹底

従業員の労働時間を適切に管理し、十分な休憩を確保することは、安全配慮義務を果たすうえで重要です。
長時間労働や休憩不足は、心身の不調や労災リスクを高めるためです。
企業が放置すれば、過労死やうつ病といった深刻な問題につながり、損害賠償を請求される恐れもあります。
具体的な取り組みには以下があげられます。
- 勤怠管理システムで労働時間を正確に把握する
- サービス残業を防ぐルールを設ける
- 法定休憩時間を必ず確保する
- 有給休暇の取得を推進する
労働時間と休憩の管理は形式的に記録するだけではなく、従業員の健康を守る仕組みとして運用することが重要です。
産業医やカウンセラーの設置

心身の健康を守るためには、産業医やカウンセラーといった専門家を配置し、従業員が相談できる体制を整えることが求められます。
社員の不調を早期に発見し、専門的な助言を得られる環境があれば、深刻な健康被害を未然に防ぐことが可能です。
- 産業医を選任し、定期面談を実施する
- 社外カウンセラーとの提携窓口を設ける
- 高ストレス者へのフォローを制度化する
- 職場復帰支援の仕組みを導入する
上記の取り組みを行えば、従業員に「安心して相談できる環境がある」という信頼感を与え、結果的に職場全体の安定につながります。
相談窓口・通報制度の整備

職場で問題が起きた際に安心して相談できる窓口や、匿名で通報できる制度を整えることは、安全配慮義務を果たすために不可欠です。
早い段階で声を拾える仕組みがあれば、ハラスメントや労務トラブルを未然に防げます。
有効な取り組みとしては次のようなものがあります。
- 社内に人事や専門部署の相談窓口を設ける
- 外部の専門機関と提携し、第三者窓口を活用する
- 匿名で通報できるホットラインを導入する
- 通報後の不利益取り扱いを禁止するルールを徹底する
相談しやすい環境をつくることが、問題の早期解決と企業への信頼維持につながるのです。
就業環境の整備(空調・安全設備など)

快適で安全な職場環境を整えることも、欠かせない取り組みです。
空調や照明などの基本的な設備が不十分だと、従業員の体調不良や事故につながります。
また、非常口や防火設備といった安全対策を怠れば、災害時に被害を招きかねません。
そのため、次のような環境整備をするとよいでしょう。
- 空調や換気設備の点検・更新
- 適切な照明と騒音対策
- 非常口や避難経路の明示
- 防火・防災設備の設置と定期点検
このように、働きやすく安全な環境を整えることは、従業員の健康を守るだけでなく、生産性や企業の信頼性を高める結果にもつながります。
監視カメラやセンサーの導入による見守り体制

監視カメラや各種センサーを導入すれば、職場における事故やトラブルを早期に発見し、従業員を守る体制を強化できます。
人の目だけでは限界があり、見逃しやすい異常を検知できる点がメリットです。
24時間体制が必要な工場や介護施設では、機械的な監視が安全配慮義務を支える有効な手段となります。
導入による効果は次のとおりです。
- 転倒や異常行動をカメラ映像で早期発見できる
- 出退勤状況を把握し、長時間労働の抑止につながる
- 防犯目的として不審者侵入を防止する
- 記録を残すことでトラブル発生時の証拠になる
結果として、テクノロジーを活用した見守り体制は、従業員の安全を守るだけでなく、企業責任を果たすうえでも役立ちます。
現地調査・お見積り無料!
監視カメラでできる安全配慮義務対策
防犯や事故防止のために活用される監視カメラは、安全配慮義務対策にも役立ちます。
ここでは、監視カメラで可能になる具体的な対策を見ていきましょう。
ここで解説すること
- 監視カメラで安全配慮義務対策ができる理由
- 実際に活用できる具体的な事例
- 監視カメラを導入する際の注意点
監視カメラで安全配慮義務対策ができる理由
監視カメラは、職場で起きている状況を映像として確認できるため、安全配慮義務を果たすうえで有効な手段となります。
人の目には限界があり、常にすべてを把握するのは不可能です。
カメラを設置することで事故やトラブルを早期に発見でき、従業員を守る仕組みを強化できます。
- 工場での転倒事故や機械トラブルをすぐに把握できる
- 介護施設での徘徊や転倒を早期に発見できる
- パワハラやいじめの証拠を記録し、再発防止につなげられる
- 不審者の侵入を抑止し、従業員の安心を守れる
職場での危険や不正を見逃さないために、監視カメラは有効な対策といえるでしょう。
安全配慮義務を対策できる監視カメラの機能
安全配慮義務を果たすには、職場環境に応じた機能を持つ監視カメラを導入する必要があります。
業種やリスクに合った機能を活用することで、事故やトラブルを未然に防げるからです。
映像記録以外に役立つ機能には次のようなものがあります。
- 遠隔監視機能:離れた場所からでも職場の様子を確認できる
- AI人検知:侵入禁止エリアの立ち入りを通知できる
- 音声録音機能:パワハラやトラブル時の証拠になる
- 赤外線機能:夜間や薄暗い場所でも監視できる
現場のリスクに合わせた機能を持つ監視カメラを導入することが、安全配慮義務の効果的な対策につながります。
監視カメラを導入する際の注意点
監視カメラを導入する際には、プライバシーへの配慮やコストを検討する必要があります。
従業員に無断で設置するとトラブルにつながりやすく、法律上の問題が発生する可能性もあるためです。
また、導入費用や運用管理が負担となるケースも少なくありません。
導入時に注意したい点は以下のとおりです。
- 従業員へ設置目的を周知し、同意を得る
- プライバシーを侵害しない位置に設置する
- 導入費用や運用コストを事前にシミュレーションする
監視カメラで「安全配慮義務」の対策をお考えの方へ
「従業員へ配慮しつつ、すぐに監視カメラを導入したい」
そんなニーズにお応えできるのが、私たちトリニティーです。
トリニティーが選ばれる理由
- レンタルなら初期費用0円で導入可能
- 月額レンタル制でコストを抑えられる
- 導入から運用まで一貫サポートがあるため安心
- AI人検知や遠隔監視など最新機能も選べる
無料の現地調査を行ったうえで、お客様に最適なプランをご提案いたします。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
よくある質問
最後に安全配慮義務についてよくある質問を紹介します。
パワハラは安全配慮義務違反になりますか?
パワハラを放置すると、従業員の健康を害し、安全配慮義務違反と判断される可能性があります。
そのため企業は、教育や相談窓口の設置などの防止策が必要です。
メンタル不調の社員への配慮は義務ですか?
企業には従業員の心身を守る安全配慮義務があり、メンタル不調への対応も含まれます。
休職や配置転換、相談窓口の整備など適切な対応をしましょう。
安全配慮義務違反の具体例は?
長時間労働を放置して過労死につながったケースや、パワハラ・いじめを見過ごした事例、学校や介護施設での事故対応を怠ったケースなどがあります。
いずれも企業や組織が損害賠償責任を負う可能性があります。
どこまで配慮すれば「違反にならない」ですか?
法律は明確な基準を示していませんが、労働安全衛生法や厚労省ガイドラインに沿った体制整備が目安です。
健康診断やハラスメント防止策、労働時間管理など一般的に必要とされる措置を講じていれば、義務を果たしていると判断されやすくなります。
安全配慮義務の415条とは?
民法415条は「債務不履行による損害賠償」に関する規定です。企業が安全配慮義務を怠り、労働者に健康被害が生じた場合、この条文を根拠に損害賠償を請求される可能性があります。
出典:e-Gov法令検索「民法 第415条」まとめ できるところから安全配慮義務対策に取り組みましょう
社員の安全と健康を守る「安全配慮義務」は、すべての企業に課せられた重要な責任です。
違反すれば、法的責任だけでなく企業イメージの低下や人材流出といった経営リスクにもつながります。
そこで有効なのが、ハラスメント防止、労務管理、健康診断の実施、そして監視カメラによる見守り体制の強化です。
早めに対策を講じた企業ほどトラブルを未然に防ぎ、社員の信頼を得られます。
トリニティーでは、初期費用0円・月額制レンタルで最新の監視カメラを導入でき、運用サポートも万全です。
安全配慮義務への取り組みを確実に進めたい方は、ぜひ一度ご相談ください。
現地調査・お見積り無料!