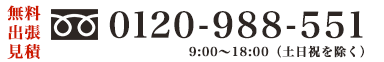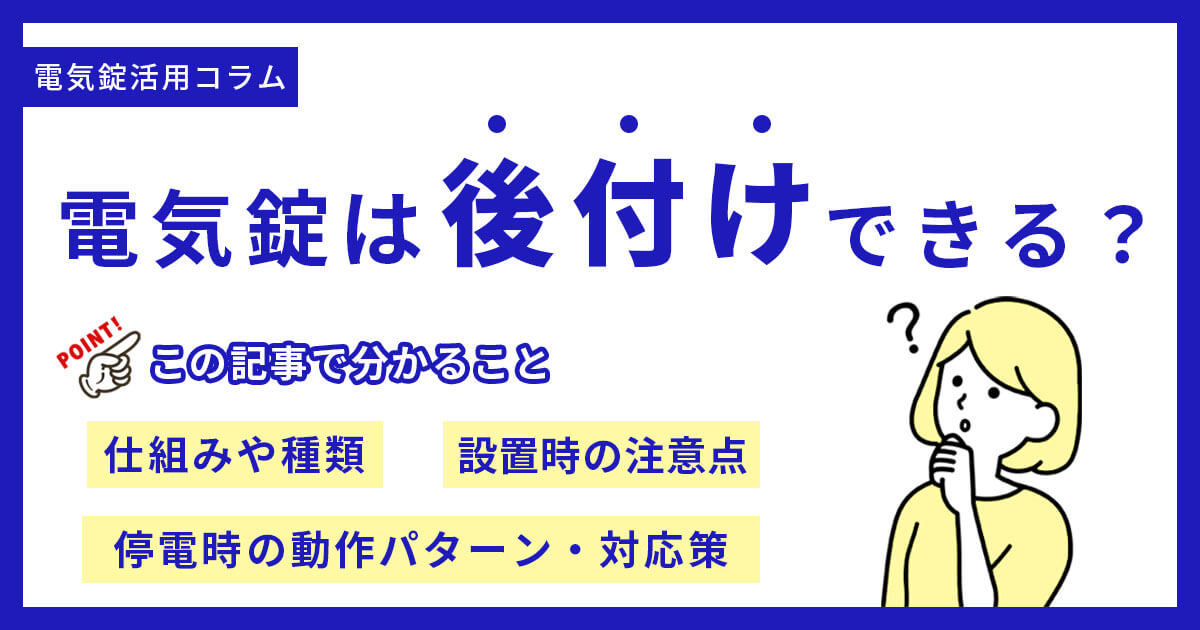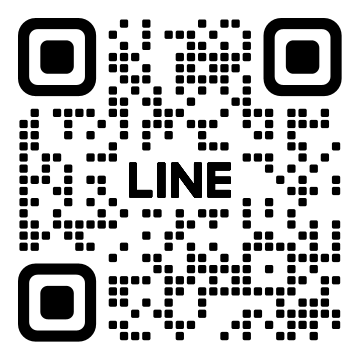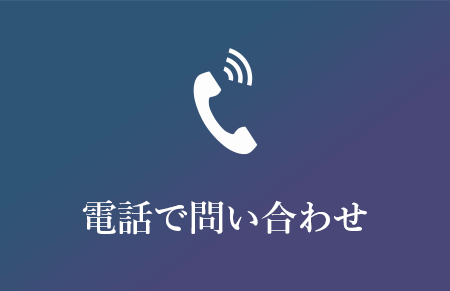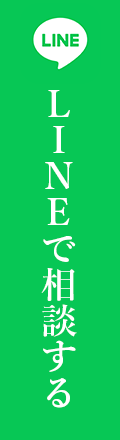電気錠は後付けできる?
種類・仕組み・停電時の動作までわかる完全ガイド
電気錠は、保育園などの教育施設をはじめ、オフィスや工場、住宅の防犯対策や入退室管理を効率化できる便利な防犯設備の一つです。
「今ある扉に電気錠を後付けできるのか」「電気錠は停電時に動作するのか」など、導入前に不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
このページでは、電気錠の種類や仕組みといった基本情報から、停電時の動作パターンや後付け設置時の注意点までをわかりやすく解説しています。ご自身に合った電気錠を選ぶ参考として、ぜひ最後までご覧ください。
電気錠とは?仕組みと基本機能をわかりやすく解説
電気錠の仕組み
電気錠とは、電気の力で施錠・解錠を行う錠前のことです。
従来のように物理的な鍵やサムターンを操作するのではなく、電気信号によって施解錠を制御します。
配線を引いて電源を供給するため、電池切れによって操作できなくなる心配がない点も特徴です。
また、ICカード・暗証番号・生体認証などの非接触・非物理的な認証方法を使用できる機種が多く、物理鍵の紛失・盗難・複製といったリスクを回避できます。
防犯性と利便性を兼ね備えた錠前として、オフィス・店舗・公共施設・住宅など、幅広い場所で活用されています。
電気錠にはどんな種類がある?
電気錠には複数の種類があり、動作の仕組みや停電時の対応方法が異なります。
設置場所や目的に応じて、最適なタイプを選ぶことが重要です。
| 種類 | 主な特徴 | 停電時の動作 |
|---|---|---|
| モーター式電気錠 | 内蔵されたモーターでかんぬきを動かして施解錠を行う | 停電前の状態を保持する ※鍵やサムターンでも開閉可能 |
| 瞬時通電施錠型電気錠 | 通電のたびに施錠・解錠を切り替える | 停電前の状態を保持する |
| 通電時解錠型電気錠 | 通電中は解錠される | 自動的に施錠される |
| 通電時施錠型電気錠 | 通電中は施錠される | 自動的に解錠される |
| 電磁錠(電磁式電気錠・電磁ロック) | 電磁石の吸着力で施錠 電気が止まると吸着が解除され解錠される |
通電が止まると解錠される |
電気錠の主な機能とできること
- 非接触・多様な認証方法で施解錠が可能
- ICカード、テンキー(暗証番号)、生体認証(指紋・顔認証など)など、複数の認証方式に対応しています。
物理的な鍵を使わずに施解錠ができ、鍵の紛失リスクもありません。 - 自動施錠で閉め忘れを防止
- ドアを閉めると自動的に施錠されるオートロック機能を搭載した製品も多く、鍵のかけ忘れによる不正侵入を防ぎます。
- 遠隔操作・一括管理が可能
- 遠隔から電気錠を操作したり、複数の扉を一括で管理したりすることが可能です。
たとえば、非常口を一斉に施解錠する操作や、施設全体の電気錠を一元管理する使い方もあります。 - タイマー機能で時間帯を制御
- 施錠・解錠の時間を設定できるタイマー機能を備えた製品もあり、利用環境や目的に応じて柔軟な運用が可能です。
- 他のシステムとの連動でセキュリティ強化
- 電気錠は、警備システムや火災報知器、入退室管理システムなどとの連動も可能です。
火災発生時に複数の電気錠を一斉に解錠したり、入退室の履歴を記録して従業員の管理やセキュリティ対策にも活用できます。
電気錠は、電気による施解錠、非接触認証、遠隔管理、オートロックなどの機能を備えた、利便性と防犯性を両立した錠前です。
導入する環境や目的に応じて適切なタイプを選ぶことで、安心でスマートな空間づくりを実現できます。
弊社トリニティーでは、防犯カメラをはじめとする各種セキュリティ機器を取り扱っており、電気錠の設置にも対応しております。
電気錠を活用したセキュリティ対策をご検討中の方は、まずはお気軽にご相談ください。
電気錠と電子錠の違いとは?
電子錠は、電池で動作する錠前です。配線工事が不要なため、大掛かりな施工をせずに取り付けられる点が大きなメリットです。
本体価格も比較的安価な製品が多く、電気錠に比べて導入コストを抑えやすいという特徴があります。そのため、主に個人宅の玄関扉などで使用されるケースが多く見られます。
一方で、電子錠は電池が切れると施解錠できなくなるリスクがあり、定期的な電池交換が必要です。
また、自分で取り付ける際に設置に失敗してしまう可能性もあるため、施工には十分な注意が必要です。
現地調査・お見積り無料!
今ある扉に電気錠を後付けできる?設置時の注意点
現在お使いの扉に電気錠を後付けできるかについては、基本的に木製や金属製など一般的な扉であれば後付けは可能です。
ただし、扉の厚み・材質・耐久性・設置位置などによっては、電気錠の設置が難しいケースもあります。
ここでは、後付けの際に確認しておくべき注意点をご紹介します。
後付けできない扉・注意が必要な扉の例
電気錠を後付けで設置するには、扉の構造や状態が適していることが重要です。
以下のような扉には、設置が難しい、または特別な対応が必要となる場合があります。
- 厚みが薄く、耐久性が低い扉(例:アルミ製の一枚扉など)
- ガタつきや歪みがある扉(正しく取り付けできず、交換が必要になることもあります)
- ガラス面が多い扉(ガラス部分には電気錠を設置できません)
- 両開き扉(片側を固定する必要があります)
- 引き戸で閉じた際に隙間が生じる扉
特に、厚みが不十分な扉や引き戸への後付け設置は難しいケースが多いため、代替案として電磁錠(電磁ロック)を採用する場合もあります。電気錠の後付けを検討する際は、専門業者に依頼し、設置予定の扉を事前に確認してもらうことをおすすめします。
電気錠の導入はトリニティーにお任せください!
弊社では、防犯カメラ設置だけでなく、電気錠や電磁錠を活用した入退室管理システムの導入にも対応しています。
これまでに、保育園・幼稚園・福祉施設など、さまざまな施設への電気錠導入実績がございます。
セキュリティ強化や効率的な入退室管理をご検討の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
後付け設置時の主な注意点
配線工事が必須
電気錠の動作には電力が必要なため、後付け設置には配線工事が不可欠です。
扉のデザインや美観を重視する場合は、配線ルートや工事内容について事前にしっかり確認したうえで、導入の可否を検討することをおすすめします。
扉への加工が発生する場合がある
一般的な鍵と電気錠では、取り付け寸法や構造に違いがあります。
このため、新たな穴を開けて施工する必要が生じるケースも少なくありません。既存の鍵穴と位置が合わない場合は、プレートを設置し、穴を塞ぐなどの作業が必要になることもあります。
また、電気錠の利用に伴い、テンキーや顔認証といった認証リーダーの取り付けが必要になる場合があります。
停電時の対応
停電時における電気錠の動作は、製品の種類によって異なります。適切な対策を講じていないと、停電が発生した際に扉が解錠されたままになったり、締め出されてしまったりといったトラブルにつながるおそれがあります。
そのため、設置前に電気錠の動作パターンを理解し、設置場所に適した製品を選定することが重要です。
電気錠の設置は専門業者への依頼がおすすめ

電気錠は、多くの一般的な扉に後付けで設置可能ですが、扉の材質・厚み・取り付け位置などによっては、設置できないケースも存在します。
「この扉に取り付けられるのか?」「どの製品が最適なのか?」といった判断には、専門業者に相談することをおすすめします。
専門業者であれば、現場の扉の状態を確認したうえで、最適な製品の選定と安全な設置工事を行うことができます。
弊社トリニティーでは、電気錠・電磁錠の導入実績が多数ございます。
障害者施設、保育園・学校などの教育施設、マンションや店舗など、さまざまな現場に対応してきました。
安心して電気錠を導入したいとお考えの方は、まずはお気軽にご相談ください。
電気錠の設置はトリニティーへ!
まずはお気軽にご相談ください
停電時に電気錠はどうなる?動作パターンと安全対策
停電時の主な動作パターン
電気錠は、その名のとおり電気の力で施錠・解錠を行うため、停電が発生すると基本的に動作しなくなります。
ただし、停電時に「施錠されるのか、それとも解錠されるのか」は、導入している電気錠のタイプによって異なります。
主に、以下の3つの動作パターンに分類されます。
1.停電時に解錠される(停電時解錠型)
電気が通っている間は施錠されており、停電時には自動で解錠されます。
防災を優先したタイプで、マンションのオートロックや非常口、老人ホームなどに使用されます。
2.停電時に施錠される(停電時施錠型)
電気が通っている間は解錠されていて、停電時には自動で施錠されます。
防犯性を優先したタイプで、重要な資産や機密を守りたいなどセキュリティ性が求められる場所に向いています。
3.停電直前の状態を保持する(停電時保持型)
停電直前の状態(施錠または解錠)をそのまま保持します。
外からは鍵で解錠、内側からはサムターンなどで操作できるため、住宅の玄関・倉庫などさまざまな場所で使用されます。
導入前に確認必須!停電時の対応策とは
停電時のリスクに備えるには、電気錠の仕様や設置環境に応じた対策を、あらかじめ講じておくことが重要です。
- 停電時の動作パターンを把握する
- 電気錠は、製品タイプによって停電時に「施錠される」「解錠される」「状態を保持する」といった動作が異なります。
導入前に必ず仕様を確認し、設置場所に適した機能を選びましょう。 - バッテリーやUPSの有無を確認する
- 内蔵バッテリーを搭載した機種を選ぶ、または外付けバッテリーやUPS(無停電電源装置)を併用することで、停電時にも一時的に電力を供給できます。ただし、UPSは使用していなくても定期的なバッテリー交換の必要があるため、コストがかかる点には注意が必要です。
- 手動解除機能の有無を確認する
- 物理鍵やサムターンでの手動解錠が可能であれば、停電時でも安全に出入りできます。
たとえば、マンションなどでは、外部からボタン操作で解錠できるタイプもあり、ボタンを押すとブザー音で解錠を知らせる仕組みを取り入れることも可能です。 - 停電時の対応マニュアルを整備・周知する
- 停電時の対応手順や操作方法を、あらかじめ関係者に周知しておくことで、緊急時の混乱を防ぐことができます。
オフィスビル、介護施設、商業施設などでは、管理者・従業員・職員向けにマニュアルを作成し、緊急時の行動や操作方法を明確にしておくことが重要です。
設置場所によって異なる電気錠の選定ポイントとは?
電気錠の停電時の動作を選ぶ際には、「防犯性」を優先すべきか、「防災性」を重視すべきかを明確にし、設置場所の用途に応じて判断することが重要です。
災害や停電時といった非常時にも安全に対応できるよう、あらかじめ使用環境に合った電気錠のタイプを選定しておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
以下に、代表的な設置場所ごとの推奨タイプと選定ポイントをまとめました。
| 設置場所 | 推奨タイプ | 選ぶ理由・ポイント |
|---|---|---|
| マンションの オートロック |
通電時施錠型(停電時:解錠) | 避難時に住人の安全確保が最優先 |
| 避難経路・非常口 | 通電時施錠型(停電時:解錠) | 緊急時に避難経路を確保するため |
| サーバー室・金庫 | 通電時解錠型(停電時:施錠) | 停電中も外部侵入を防ぐため |
| オフィスの出入り口 | 停電直前の状態を保持 通電時解錠型(停電時:施錠) |
利便性と防犯性の両立が必要 |
| 通用口・共用出入口 | 通電時解錠型(停電時:施錠) | 出入りが多く防犯性も求められる |
| 門扉 | 通電時施錠型(停電時:解錠) 通電時解錠型(停電時:施錠) |
屋外設置には防犯と安全の両立が必要 |
電気錠には、停電時に「解錠されるタイプ」と「施錠されるタイプ」に大きく分けられます。導入前には、その場所に求められる安全機能や運用方針を明確にし、非常時の管理体制や対応フローも含めたトータルでの設計が不可欠です。
用途に適した電気錠を選ぶことで、日常の安心だけでなく、非常時の安全確保にもつながります。
後付けできる?停電したら?
電磁錠に関するよくある疑問にお応えします!
電気錠はどんな扉でも後付けできますか?
基本的には、既存の扉に後付けで設置することが可能です。
ただし、扉の厚みが薄い場合や、ガラス面に取り付ける必要がある場合、また扉の建て付けが悪い場合などは、設置が難しくなることがあります。そのため、導入を検討する際は、専門業者に依頼して現地調査を行い、扉の状態を確認してもらうことをおすすめします。
電気錠は停電したらどうなりますか?
電気錠には、停電時に「自動的に解錠されるタイプ」「施錠されるタイプ」「停電直前の状態を保持するタイプ」があります。設置場所で求められる防犯性や安全性に応じて、最適な動作タイプを選ぶことが大切です。
電気錠の耐用年数はどのくらい?
日本ロック工業会のガイドラインによると、電気錠の耐用年数は一般的に7~10年程度が目安とされています。
ただし、開閉頻度が多い扉の場合、故障や動作不良が起こる可能性もあります。そのため、定期的なメンテナンスを実施することをおすすめします。
電子錠の設置には資格が必要ですか?
資格は必要ありません。専門知識がなくてもDIYで簡単に取り付けることができるタイプも多くあります。
ただし、簡易的な製品は扉から外れやすかったり、衝撃に弱かったりする場合もあります。
セキュリティ性を重視する場合は、より耐久性の高い電気錠を専門業者に依頼して設置することをおすすめします。
電気錠の導入実績をご紹介|オフィス・幼稚園・介護施設など
電気錠の設置は、トリニティーにお任せください。弊社では、中部・関東エリアを中心に、保育園・工場・オフィスなど、さまざまな施設への電気錠の導入を行ってまいりました。
ここでは、実際にご対応させていただいた導入事例の一部をご紹介いたします。
セキュリティ対策や入退室管理に電気錠の導入をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。
※プライバシー保護の観点から、一部情報を変更して掲載している場合がございます。
電気錠を後付けするなら専門業者への依頼がおすすめ

このページでは、電気錠の仕組みや種類、後付け設置時の注意点、停電時の動作パターンや対策について、わかりやすくご紹介しました。
電気錠の後付けは、多くの扉に対応できますが、扉の材質や厚み、設置位置などの条件によっては、施工が難しいケースもあります。さらに、配線工事や扉の加工が伴うケースも多いため、確実で安全に導入するには、専門業者に依頼することをおすすめします。
トリニティーでは、保育園・福祉施設・オフィス・工場・集合住宅など、さまざまな施設への電気錠の導入実績がございます。
現地調査から設置工事まで対応可能です。「この扉に取り付けられるか心配」「停電時の安全対策も含めて提案してほしい」といったご相談にも、弊社スタッフが、丁寧に対応いたします。ご検討の際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。