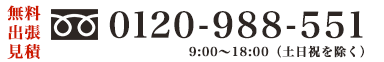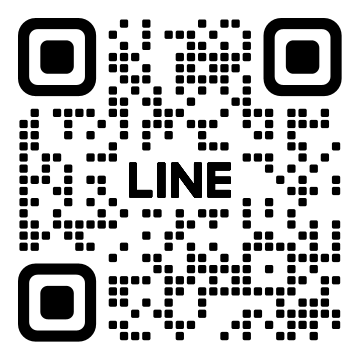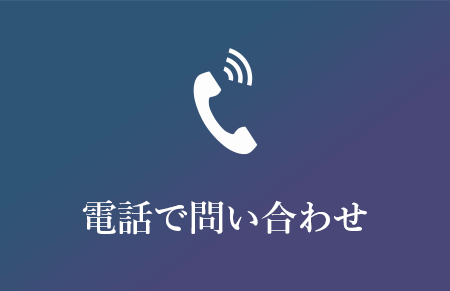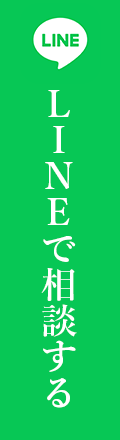職場の監視カメラはパワハラ対策に有効?
違法にならない設置方法も解説
「最近、職場でのパワハラやセクハラが心配…」
「問題が起きても、証拠がなくて対処できない」
そんな悩みを抱えている経営者や人事担当者の方も多いのではないでしょうか。
リモートワークや多様な働き方が広がる中で、目の届かない職場でのハラスメント対策は重要性を増しています。放置すれば離職や企業イメージの悪化につながりかねません。
そんな中、職場への監視カメラ導入が「パワハラの抑止力」として注目されています。
正しく設置・運用すれば、法的リスクを回避しつつ、職場の透明性を高め、問題の早期発見・解決にもつながります。
この記事はこんな方におすすめ
- 職場に監視カメラを設置してハラスメントを防止したい経営者・人事の方
- 監視カメラを導入しても法律的に問題がないか不安な方
- 実際のトラブル事例と、導入によるメリットを知りたい方
社員の安全と安心を守る職場づくりのために、ぜひこの記事を参考にしてみてください。
職場の監視カメラ設置はパワハラになるのか?
職場に監視カメラを設置する際に、「パワハラとみなされるのでは?」という懸念を抱く方もいるでしょう。
結論をいうと、職場の監視カメラはルールを守って適切に設置すれば、パワハラとは見なされません。
ここでは、監視カメラの設置に関してよくある法律面の疑問を取り上げ、それぞれのポイントをわかりやすく解説します。
ここで紹介すること
- 労働基準法的には問題ない
- パワハラになるケース
それぞれ順番に解説します。
労働基準法的には問題ない
職場への監視カメラ設置は労働基準法に違反するのではないか、と心配される方も多いです。
しかし、原則として問題はありません。ポイントとなるのは、「目的の正当性」と「従業員への事前説明」です。
労働基準法では、企業側が安全管理や労務管理の一環として監視カメラを設置することは、正当な業務目的と見なされます。
ただし、従業員に無断で設置した場合には、プライバシー権の侵害に該当する可能性があるため注意しましょう。
たとえば、入口や共有スペースなど、監視の目的が明確で、なおかつ業務に関連する場所への設置であれば、法的にも認められるケースがほとんどです。
また、設置前に「どこに・なぜ設置するのか」を説明し、同意を得るとトラブルを未然に防げます。
このように、労働基準法の趣旨を理解し、適切なプロセスを踏んで設置すれば、監視カメラの導入は違法とはならず、むしろ労働環境の改善にもつながります。
パワハラになるケース
監視カメラの設置は、場合によってはパワハラと認定されることもあるため注意しましょう。
問題となるのは、「目的が不明確」または「監視の仕方が行き過ぎている」場合です。
たとえば以下のようなケースでは、パワハラと見なされる可能性があります。
- 特定の社員だけを常時録画
- トイレや休憩室など私的空間に近い場所への設置
- 業務に関係のない範囲での録音や録画
正当な理由と透明性を欠いた監視は、企業が逆にパワハラの加害者とされるリスクを高めます。
監視の目的・対象・方法を明確にし、全社員に丁寧に説明しましょう。
職場に監視カメラを導入する4つのメリット
職場に監視カメラを導入して得られるメリットは、トラブルの証拠を残すだけではありません。
業務の効率化や企業全体の信頼性向上にもつながるため、導入を検討する価値があります。
ここでは、企業が監視カメラを導入することで得られる主なメリットを4つ紹介します。
- ハラスメントの防止
- 犯罪や不正行為の抑止
- 労務管理
- 業務の効率化
それぞれ見ていきましょう。
ハラスメントの防止
監視カメラの設置は、パワハラやセクハラの防止に効果があります。カメラがあると社員の言動に注意が向き、不適切な行為が起こりにくくなるためです。
職場にカメラがあると、「見られているかもしれない」と感じて、普段の言動に気をつけるようになります。
実際に、カメラの設置をきっかけにハラスメントが減ったと感じる企業も少なくありません。
具体的には、以下のような場面でカメラの存在が意味を持ちます。
- 上司から部下への強い口調による指導
- 社員同士のトラブルが繰り返される現場
- 第三者がいない空間でのセクハラ行為
こうしたケースでは、カメラが「記録している」という事実が心理的な抑止力となり、問題の発生そのものを防ぎます。
ハラスメントのない環境をつくる第一歩として、監視カメラの導入は前向きに検討すべきでしょう。
犯罪や不正行為の防止
監視カメラは、社内での犯罪や不正を未然に防ぐ手段になります。
企業の内部で起こる問題は、以下のように目の届きにくい場所で行われるケースが多いためです。
たとえば、以下のような事例では、監視カメラが有効に働きます。
- レジ周辺での売上金の扱いを記録し、金銭トラブルを防止
- 出入り口に設置することで、無断持ち出しや不審な出入りを抑止
- 社内の物品倉庫や管理エリアでの不正利用をチェック
記録が残ると、問題が起きた際に「何が起きたか」を把握できるため、早期に対応できます。
防犯カメラを企業に導入すれば、従業員に安心感を与えながら、企業の信用や資産を守る役割も果たせる点もメリットです。
労務管理
監視カメラは、パワハラやセクハラなどのハラスメントや不正の防止にに加え、労務管理にも効果的です。勤務の様子を映像として記録できるためです。
たとえば、タイムカードだけでは把握が難しい出退勤の実態も、映像によって実際の動きを裏付ける材料として活用できるでしょう。労働時間の申告と行動が一致しているかどうか、記録をもとに判断しやすくなります。
このように監視カメラを導入するれば、管理者の目が届きにくい場面も映像で確認できるため、労務管理の精度が向上します。
業務の効率化
監視カメラの導入は、日常業務の効率化に役立ちます。映像を活用することで、現場の動きを把握できるため、無駄や改善点を見つけやすくなるためです。
たとえば、スタッフの動線や作業手順を映像で確認すると、非効率な動きや作業の重複を把握できます。
他にも以下のように業務の効率化に活かせます。
- 接客や来客対応の様子を映像で確認し、サービスの質を改善する
- 業務中の待機時間や空き時間を見つけ、作業効率を見直す
- 作業手順やルールの遵守状況をチェックし、社員教育の改善につなげる
日常の業務を映像として記録し、データに基づいて改善を進められるのが監視カメラ導入のメリットです。
会社に監視カメラを置くべき4つの理由
ここでは、会社に監視カメラを導入すべき理由を4つ紹介します。
いずれも実務上の課題に直結する内容であり、導入の判断材料として役立つでしょう。
- ハラスメントの実態をつかむ
- 対策しないと労働基準局が介入する
- 離職率が上昇する
- 世間からの評判が落ちる
それぞれ順番に解説します。
ハラスメントの実態をつかむ

会社に監視カメラを置くべき理由の1つ目は、「ハラスメントの実態をつかんで立証するため」です。
厚生労働省が発表した調査によると、過去3年間にパワハラを経験した人の割合は、男性が19.4%、女性が19.2%となっています。また、パワハラを受けた経験がある人のうち、30%以上が繰り返し被害を受けているため、対策は必要不可欠です。
被害を立証するためには、証拠が必要になるため、監視カメラを設置するとよいでしょう。
参考:厚労省「職場のハラスメントに関する実態調査(令和5年度報告書)」
監視カメラの映像以外にも押さえておきたい証拠には、以下のようなモノがあります。
- LINEやメールなど、やりとりの履歴がわかる文面
- ボイスレコーダーなどで録音した音声データ
- 病院を受診した場合、医師の診断書
このように、パワハラ被害を立証するためは、監視カメラの設置が不可欠です。
対策しないと労働基準局が介入する

2つ目の理由は、ハラスメント対策を怠っていると、労働基準監督署(労基署)からの指導や介入を受ける可能性があるためです。
厚生労働省は企業に対して「職場のハラスメント防止措置」を義務づけており、対応が不十分と判断された場合には、行政指導が入る仕組みになっています。
たとえば、以下のようなケースでは、労基署の介入につながるおそれがあります。
- ハラスメント被害の訴えに対して会社が何も対応していない
- 実態の調査を行わず、加害者・被害者の主張だけで判断している
- 客観的な証拠がないため、事実があいまいなまま放置されている
こうした事態を防ぐためにも、監視カメラを活用して日常のやり取りを記録し、客観的な事実を確認できる環境を整えてることが大切です。
企業が積極的に対策を行っている姿勢を示すことは、行政対応への備えになるだけでなく、社員が安心して働ける職場環境づくりにもつながります。
離職率が上昇する
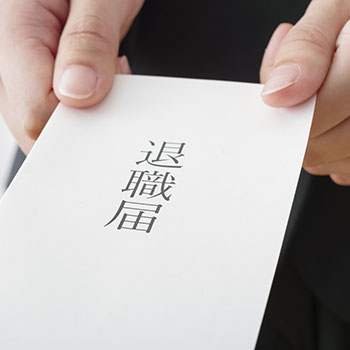
3つ目の理由は職場におけるハラスメントや不公平な扱いが放置されていると、社員の離職率が高まるためです。
ハラスメントは、業務効率やチームワークに悪影響を及ぼすだけでなく、社員のメンタルにも深刻なダメージを与えるため、早めに解決する必要があります。
たとえば、以下のような兆候が見られる職場は要注意です。
- 特定の部署や上司のもとで退職者が続出している
- 人間関係のストレスを理由に、体調を崩す社員が目立つ
- トラブルがあっても、事実確認やフォローが行われていない
このような問題を防ぐには、日常のやりとりを見える化できる仕組みが必要です。
監視カメラの映像は、言葉や感情では伝えにくい状況を記録し、冷静に対応するための手がかりとなります。結果として、社員が安心して働ける環境が整えば、離職率の低下にもつながるでしょう。
世間からの評判が落ちる

4つ目の理由は、ハラスメントや職場のトラブルを放置していると、その事実が外部に広がり、企業の評判を損なうおそれがあるためです。
たとえば、SNSや口コミサイト、ニュース記事などで問題が発信されてしまうと、関係者だけでなく、取引先や求職者にも悪印象を与えかねません。
こうした事態を未然に防ぐには、社内で問題が起きた際、早期に正確な情報を把握できる仕組みが必要です。監視カメラは、そのための有効なツールのひとつといえるでしょう。
トラブルに適切に対応する企業であると認識されれば、結果として世間からの信頼を維持・向上させることにもつながります。
監視カメラを適切に運用すれば、職場の問題解決に役立ちます。
導入を検討する場合は、ぜひ弊社にご相談ください。無料で現地調査を行い、最適なプランをご提案します。
【事例紹介】監視カメラ導入で職場のパワハラ問題を改善
実際にパワハラが発生していた職場で、監視カメラの設置が状況の改善につながったケースは少なくありません。
ここでは、弊社が対応した事例の中から、効果が見られた2つのケースを紹介します。
ここで紹介すること
- 指導とパワハラの境界線を映像で可視化
- 被害者のメンタルケアと再発防止への活用
指導とパワハラの境界線を映像で可視化
パワハラか適切な指導か。この線引きは曖昧で、当事者の立場や経験によって受け取り方が異なります。
そのため、企業内での認識のズレがハラスメントを引き起こす原因となるケースは珍しくありません。
実際に、外部通報窓口のある企業から、「現場の教育の様子を撮影・録音し、遠隔で確認できるようにしてほしい」と依頼をいただいた事例がありました。目的は、日々の指導が適正かどうかを客観的に確認し、トラブルの芽を早期に摘むことでした。
このような課題が起こる背景には、次のような問題があります。
- 「教育」と称して不適切な態度や言動をとる指導者が存在する
- 上司と部下の間で立場の差が大きく、部下が声を上げづらい
- 不快感があっても、証拠がなければ対処が難しい
監視カメラとマイクで指導の様子を記録し、社外からも確認できるようにしたことで、社内の「常識」が適切かどうかを見直すきっかけが生まれました。
映像と音声を通じて、指導の妥当性を社内で共有できるようになり、境界線の共通理解も深まっています。
被害者のメンタルケアと再発防止に効果的
近年では、部下から上司への「ハラハラ」が報告されるなど、職場のハラスメント問題は複雑化しています。
また、上司が過剰に部下に気を遣い、必要な指導を避けてしまうことで、かえって職場の秩序が乱れるケースもあるでしょう。
こうした職場環境では、以下のリスクが高まります。
- ハラスメントが常態化し、誰も注意できない雰囲気になる
- 被害者が精神的に追い込まれ、早期退職者が増える
- 問題行動が曖昧なまま放置され、社内に不信感が広がる
ある企業では、社員の主な活動エリア(デスク周辺、会議室、休憩室、廊下など)に威圧感を与えないドーム型カメラを設置し、職場を「見守る」環境を整えました。
このような配慮のある監視体制によって、社員の精神的な負担が軽減されるとともに、問題行動の抑止・記録ができるようになりました。
ハラハラとは?
ハラハラ(ハラスメントハラスメント)とは、ハラスメントに対する過剰な反応や誤解によって、本来必要な指導や注意まで「ハラスメントだ」と訴えられてしまう行為を指します。
特に最近では、上司がパワハラと誤解されることを恐れ、必要な指導を控えることで、職場の秩序や業務効率が乱れてしまうケースが増えています。
こうした状況を防ぐためには、パワハラの定義や基準を社員全員で明確に共有し、誤解が生じないように十分周知することが重要です。
職場のハラスメント防止や防犯対策に監視カメラの導入をご検討中の方は、豊富な導入実績を持つ弊社までお気軽にお問い合わせください。
職場のハラスメントやいじめを解決する方法
職場のハラスメントやいじめを解決する方法について見ていきましょう。
ここでは、社内の問題を解決するために導入した防犯カメラや周辺機器を紹介します。
ここで紹介すること
- マイク搭載防犯カメラを設置
- 集音マイクを設置
- 隠しカメラを設置
- 防犯カメラの導入は「レンタル」がおすすめ
それぞれ見ていきましょう。
マイク搭載防犯カメラを設置
パワハラやセクハラなどのトラブルを抑止する手段には、防犯カメラの設置が効果的です。
とくにマイク搭載の防犯カメラは、音声も証拠として残せるため、職場のハラスメント被害を最小限に抑えられます。
具体的なマイク搭載の防犯カメラは以下の2つです。
TR-IP8510 / TR-IP9510

500万画素の高画質なマイク搭載の防犯カメラです。
屋内外どちらにも設置可能。映像だけでなく音声も記録できるため、より確かな証拠を残せます。
社内など威圧感を避けたい場所にはドーム型カメラが適しています。
一方、出入り口や駐車場など監視を強化したい場所では、威嚇効果のあるバレット型カメラがおすすめです。さらに、AI機能を搭載しており、不審者の侵入を検知するとスマホへの通知も可能。
【おすすめポイント】
- マイク内蔵で音声の録音が可能
- 赤外線機能で夜間も白黒で鮮明な映像を撮影
- AI侵入検知機能により、侵入者検知時にスマホ通知が可能
集音マイクを設置

弊社では、防犯カメラとは別に設置できる集音マイクをご用意しています。
防犯カメラの設置位置が音声録音に適さない場合は、別の場所に集音マイクを設置する方法がおすすめです。用途や環境に合わせて柔軟な調整が可能です。
カメラから離れた場所の音声をしっかり記録したい場合は、別途マイクを設置することで録音の精度が向上し、職場の安全性や安心感の向上につながります。
隠しカメラを設置
職場でハラスメントや内部不正が発生していている場合、証拠を確実につかむためには「隠しカメラ」が有効です。当事者がカメラの存在を意識しない状況でこそ、実態が明らかになります。
たとえば、上司や同僚が監視の目を避けて問題行動を取っている場合、設置済みのカメラでは証拠が残らないこともあるでしょう。そうしたケースでは、小型で目立たないカメラを使い、必要なタイミングだけ録画する方法が適しています。
ただし、運用する際は、プライバシーを尊重し、必要最低限の範囲に限定しましょう。職場で実際に問題が発生している場合には、隠しカメラの導入も検討してみてください。
※隠しカメラの設置は、犯罪やトラブルの解決を目的とした場合のみ承っております。いたずらや犯罪を助長する目的でのご依頼はお断りいたします。
防犯カメラの導入は「レンタル」がおすすめ
職場のハラスメント対策で防犯カメラを導入したいけれど、費用が気になるという方には、レンタルプランがおすすめです。
弊社のレンタルプランなら、機器選定・設置工事・保守をすべて含め、初期費用0円・月額費用のみで導入いただけます。
また、機器故障時の出張修理やHDDなどの消耗品の交換も無償で対応。長期間、安心して防犯カメラをご利用いただけます。
初期費用を抑えつつ高品質な防犯カメラを導入できるレンタルプラン。職場への防犯カメラ設置をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
職場に防犯カメラを設置する際の注意点
防犯カメラは職場環境の改善やトラブル防止に効果的ですが、設置方法を誤ると従業員との信頼関係を損なうリスクがあります。ここでは、職場に防犯カメラを設置する際に注意すべき6つのポイントをご紹介します。
注意すべき6つのポイント
- プライバシーに配慮した設置場所を選ぶ
- 設置の目的と範囲を社員に明確に説明する
- 映像管理の担当者を明確にする
- カメラ運用に関する社内ルールを整備する
- 映像データの保存と取り扱いを厳重に管理する
- 公的機関のガイドラインに沿った設置を行う
それぞれ順番に確認しましょう。
プライバシーに配慮した設置場所を選ぶ
職場に防犯カメラを導入する際、注意すべきなのが従業員のプライバシーです。防犯やハラスメント対策が目的でも、監視されていると感じてしまうと心理的なストレスになります。
たとえば、更衣室・休憩室・トイレ付近などの場所はカメラの設置を避けるべきでしょう。
これらの場所にカメラを設置した場合、たとえ録画されていなくても「監視されている」と感じるだけで、不快感や不信感を与える可能性が高くなります。
このような問題を防ぐには、業務スペースや共用部分の中でも、カメラの設置目的に合致した場所を慎重に選ぶことが大切です。事前に社員へ説明を行い、理解を得ながら設置を進めることで、不安や誤解を防ぎましょう。
設置の目的と範囲を社員に明確に説明する
防犯カメラを導入する場合、社員に設置の目的と意図を説明しましょう。不明確なまま進めると、不信感を抱きやすくなり、社内の雰囲気が悪化する可能性もあるからです。
対策として「なぜこの場所に設置するのか」や「どこまで映像が記録されるのか」などの情報を社員に伝えましょう。
上記の情報を説明しないまま運用を始めてしまうと、「自分たちは信用されていないのでは」と感じる社員が出てくることもあります。企業の誠実な姿勢が伝われば、防犯カメラは「信頼される管理ツール」として受け入れられるでしょう。
映像管理の担当者を明確にする
防犯カメラの映像には、社員の行動や会話など、プライバシーに関わる情報が含まれるため、誰が映像を確認・管理するのかを明確にしておきましょう。
担当者が曖昧だと、「誰がいつ・何のために映像を見ているのか」が不透明になり、社員から不信感を招いてしまうためです。
場合によっては、プライバシーの侵害として問題視されるでしょう。
トラブルを避けるためには、以下のような運用ルールを決めておくのがおすすめです。
- 映像を閲覧・管理できる担当者を明確にする
- 映像の取り扱いに関する権限や手順を文書化して共有する
- 不適切な閲覧や流出を防ぐため、アクセス権限を限定する
防犯カメラの映像は「証拠」にもなりうる一方で、使い方を誤れば社員の信頼を損ねてしまうリスクもあります。
そのため、誰がどのように映像を扱うかを明確にして、安心感のある運用体制にしましょう。
カメラ運用に関する社内ルールを整備する
防犯カメラを導入する場合、社内ルールを整備しておきましょう。ルールがないまま運用を開始すると、情報漏えいや不正利用のリスクが高まるためです。トラブルを避けるため、あらかじめ以下のような方針を決めておくとよいでしょう。
- 映像をどのような目的で使用するのか
- 録画データの保存期間と削除手順
- 映像を閲覧・提供できる範囲(社内・外部機関など)の制限
- 映像の扱いに関する違反時の社内対応や罰則の設定
ルールを就業規則や社内マニュアルに盛り込んで、カメラ運用を適切に行ってください。
映像データの保存と取り扱いを厳重に管理する
防犯カメラの映像は、トラブル時の重要な証拠になる一方で、従業員のプライバシーが含まれるデリケートな情報でもあります。そのため、保存や閲覧の方法には注意しましょう。
管理が甘いと、情報漏えいや不正閲覧といった問題が起きるおそれがあります。特に社外への流出があれば、信頼の失墜は避けられません。
防止策としては、以下のような対応が有効です。
- 映像の保存期間を明確に設定する
- アクセス権限を限定し、不正閲覧を防ぐ
- 利用履歴を記録し、管理状況を可視化する
つまり、映像の取り扱いは「記録する以上に、どう守るか」が問われる管理業務なのです。
公的機関のガイドラインに沿った設置を行う
防犯カメラの設置は個人の権利やプライバシーを尊重するために、各省庁が示すガイドラインを参考にするとよいでしょう。
たとえば、個人情報保護委員会や厚生労働省は、目的の明確化、設置場所の妥当性、映像の適正な取り扱いなどに関する指針を示しています。これらをルールを守らずに運用すると、プライバシー侵害としてトラブルになる可能性もあります。
事前に公的機関のガイドラインを確認し、社内の運用ルールに反映させると法的トラブルを回避しやすいです。
【よくある質問】職場の監視カメラ設置について
最後に職場に監視カメラを設置するにあたって、よくある質問を解説します。
- 職場の監視カメラは人権侵害にあたりますか?
- 適切な目的で設置され、撮影範囲や管理方法に配慮されていれば、職場の監視カメラが人権侵害にあたることはありません。
- 職場の監視カメラが有罪になった判例はありますか?
- 職場の監視カメラが訴訟に発展したケースはあります。ただし、目的が不適切だった場合です。
防犯やハラスメント対策にカメラを導入し、設置目的と位置の説明を適切に行えば、訴訟になる可能性はほとんどないでしょう。
職場の監視カメラ設置はトリニティーへお任せください

職場への監視カメラ設置は、適切に運用すれば、労働基準法に違反はせず、パワハラ対策や防犯に大きな効果を発揮します。
ただし、導入時には設置の目的と場所を明確にし、社員の納得を得ることが重要です。ルールを明確に定めて運用を行えば、トラブルを防ぎ、職場環境の改善にも役立ちます。
弊社では監視カメラの設置から運用する際の注意点も含めて最適なプランをご提案いたします。現地調査・お見積りは無料です。
まずはお気軽にお電話、メール、LINEにてお問い合わせください。