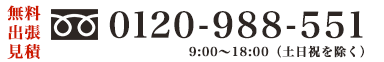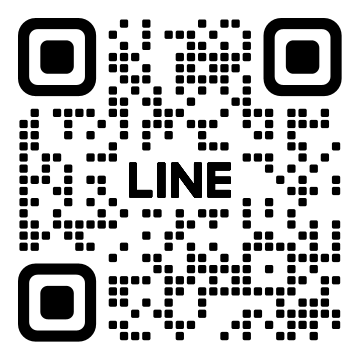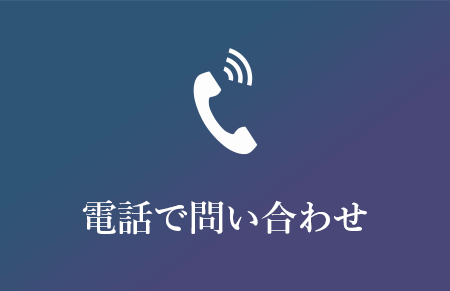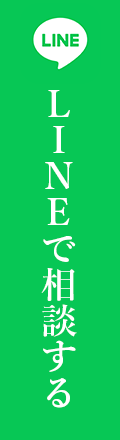老人ホームで物がなくなる理由とは?
防犯カメラの力で紛失トラブルを防止しよう
「入居者の物がなくなった」と家族に責められた経験はありませんか?
「職員が盗ったのでは」と疑われ、説明や謝罪に追われた方もいるでしょう。
老人ホームでは、洗濯物や補聴器、財布の紛失が起こりやすく、施設側が責任を問われがちです。対応を誤ると、職員の士気や施設の信用にも悪影響を及ぼします。
そこで注目されているのが、防犯カメラの導入です。
「いつ・誰が・どこで」起きたのかを映像で可視化でき、トラブルの予防や冷静な対応に役立ちます。
この記事はこんな人におすすめ
- 介護施設での紛失トラブルを未然に防ぎたいと考えている方
- 防犯カメラの活用でスタッフや施設を守りたい方
- 責任の所在を明確にし、家族からの信頼を高めたい方
施設内の安心を守るヒントとして、ぜひ本記事をお役立てください。
「防犯カメラの導入費用や設置までの期間」が気になる方は、お気軽にお問い合わせください。
老人ホームで物がなくなる原因とは?
老人ホームで「物がなくなる」と訴えがあった場合、原因は1つとは限りません。
そこで、よくある紛失の背景を整理し、次の3つのケースに分けて解説します。
物がなくなる3つの原因
- 洗濯時の取り違えや記名忘れによる誤配
- ヒューマンエラーによる管理ミス
- 盗難の可能性と施設の対応範囲
順番に見ていきましょう。
洗濯時の取り違えや記名忘れによる誤配
衣類に記名がないと、洗濯後の仕分けで別の入居者に誤って配られて紛失してしまいます。とくに下着や靴下など似たものは要注意です。
洗濯時には、名前の記入が十分か記名のない衣類がないか、確認してから行いましょう。
すべての衣類に記名を徹底し、職員によるチェック体制を強化することで、誤配のリスクを減らせます。
ヒューマンエラーによる管理ミス
介護現場では人手不足や忙しさから、物品管理のミスが起こりがちです。
たとえば、仮置きした私物を忘れる、引き継ぎが口頭だけ、リストの更新漏れなどが原因になります。
確認ルールや記録の仕組みを整えることで、こうしたミスの再発を防げます。
盗難の可能性と施設の対応範囲
入居者や職員による盗難の可能性はゼロではなく、実際に家族から「盗まれた」と指摘されるケースもあります。
ただし、施設にはできる範囲に限りがあり、以下のケースでの対応は困難です。
- 現場を目撃した人がいない
- 金銭や貴重品の保管方法が曖昧
- 契約上、施設が責任を負わないと定められている
防犯カメラを導入すれば、状況を記録でき、誤解防止につながります。
老人ホームで実際にあった紛失トラブル
老人ホームでは、物の紛失がきっかけで家族とのトラブルに発展するケースが少なくありません。信用の低下や職員の精神的負担にもつながるため、注意が必要です。
ここでは、過去に起きた具体的なトラブルと、それによる影響を3つ紹介します。
実際のトラブル例3つ
- 老人ホームで補聴器や入れ歯を紛失したケース
- 衣類の紛失とルール不足の問題点
- 財布・通帳の紛失から家族の訴訟に発展
それぞれの事例から、対策の重要性を考えていきましょう。
老人ホームで補聴器や入れ歯を紛失したケース

補聴器や入れ歯などの医療器具は、体の一部のように大切な私物です。
紛失すると、家族から強く責任を問われることもあります。
実例としては、食後の洗浄時に仮置きしていた入れ歯を紛失したケースや、就寝中に外した補聴器を職員が誤って廃棄してしまったケースなどがあります。
高額で作り直しに手間と時間がかかるため、防止策の徹底が欠かせません。
衣類の紛失がルール不足で発生するケース

ある施設では、記名のない衣類が別の入居者に配られ、家族から苦情が寄せられました。
配布時のチェックが個人任せだったことに加え、紛失時の対応ルールも曖昧で、説明が二転三転したことが原因です。
こうしたトラブルを防ぐには、記名や確認方法、対応フローを文書で統一し、職員間で共有することが欠かせません。
財布・通帳の紛失から家族の訴訟に発展したケース

ある施設では、保管場所が曖昧だった通帳が紛失し、家族が警察に相談。最終的に訴訟に発展し、施設の信用が大きく揺らぎました。
たとえ自己管理の物でも、対応を誤ると責任を問われることがあります。
こうした事態を防ぐには、「預からない」「自己管理」などの方針を明確にし、家族にも事前に共有しておくことが重要です。
老人ホームで物がなくなった場合、誰が責任を負うべきか?
紛失トラブルが起きた際、施設側が責任を問われることは少なくありません。しかし、すべての物品に対して施設が責任を負うわけではなく、明確な線引きを設けておくことが重要です。
ここでは、責任の考え方を明確にするための3つのポイントを解説します。
責任の考え方 3つのポイント
- 介護保険と現物紛失の関係を理解する
- 弁償ルールと契約書の注意点を整理する
- 老人ホームでの金銭・貴重品管理の原則を決めておく
それぞれ順番に見ていきましょう。
介護保険と現物紛失の関係を理解する
介護保険は、あくまでも介護サービスの提供に対する制度であり、施設内での私物の紛失や盗難には適用されません。
しかし、家族の中には「介護保険で補償されるのでは」と誤解している方もいます。
こうした認識のズレがトラブルにつながるため、あらかじめ契約時に補償の対象外であることを丁寧に説明しておくことが大切です。
弁償ルールと契約書の注意点を整理する
紛失が起きた際、施設に弁償を求める場合がありますが、すべてに応じる義務があるわけではありません。
対応を明確にするためには、契約書の記載内容が重要です。
たとえば、契約書で「貴重品の自己管理」「施設は補償しない」と明記していれば、過剰な請求を防げます。一方で、曖昧な記述では責任の所在が不明確になり、トラブルが拡大してしまうでしょう。
契約時には補償範囲と管理責任について、具体的に記載しておくことが不可欠です。
老人ホームでの金銭・貴重品管理の原則を決めておく
金銭や通帳などの貴重品は、管理方法が不明確だと紛失や盗難のリスクが高まります。
事前に施設としての管理方針を定め、入居者や家族に共有しておくことが必要です。
たとえば「現金は原則持ち込み禁止」「通帳は家族が管理」など、ルールを明文化しておけば、責任の所在も明確になります。
あとからのトラブルを防ぐためにも、入居前の説明と同意を欠かさないようにしましょう。
弁償を求められたとき、施設はどう対応すべきか?
利用者やその家族から紛失の責任を問われ、「弁償してほしい」と求められることは珍しくありません。
対応を誤れば、信頼低下や訴訟リスクを招く可能性もあるため、事前に対応フローを整え、職員間で共有しておくことが重要です。
ここでは、弁償を求められたときに施設側がとるべき対応を3つの視点から解説します。
施設側がとるべき3つの対応
- 家族に責められたときの対応フローを確認しておく
- 曖昧な責任の判断基準を整理する
- 警察・弁護士・第三者機関の役割を理解しておく
順番に確認していきましょう。
家族に責められたときの対応フローを確認しておく

家族から強く責められた際、職員が単独で対応するとトラブルが悪化する恐れがあります。
そのため、あらかじめ対応フローを整え、「事実確認は現場職員、説明は責任者」「記録を残す」などの役割分担を明確にしておきましょう。
曖昧な責任の判断基準を整理する
老人ホームで物がなくなった際、施設側と入居者側の責任が曖昧だと、話し合いがこじれやすくなります。
そのため、以下のような判断基準を事前に整理しておくことが大切です。
- 職員が直接関与していたか
- 保管ルールは守られていたか
- 入居者側に過失はないか
基準を明確にしておけば、感情的な対立を防ぎやすくなります。
警察・弁護士・第三者機関の役割を理解しておく

紛失や盗難が深刻化した場合、施設だけで抱え込まず、外部機関と連携することが重要です。
たとえば、盗難時は警察、賠償や契約トラブルには弁護士、中立的な助言が必要な場合は第三者機関など、状況に応じた対応先を把握しておきましょう。
外部の力を活用することで、施設と家族の信頼関係を保ちやすくなります。
第三者に相談する場合は、防犯カメラの映像や音声などの証拠があると、問題を伝えやすいです。
導入を検討する場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
老人ホームの紛失・盗難を防ぐ具体的な対策
紛失や盗難は完全には防げないものの、日常業務の中で基本的な対策をすれば、トラブルを未然に防げます。
重要なのは、職員だけに負担をかけるのではなく、仕組みとしての管理体制を整えることです。
ここでは、介護施設で実践できる基本的な3つの対策を紹介します。
基本的な3つの対策
- 持ち物に名前記入・管理リストの作成
- 洗濯・清掃時のチェック体制強化
- 定期的な居室内の私物点検と記録の保存
持ち物に名前記入・管理リストの作成
紛失を防ぐ第一歩は、すべての持ち物に名前を記入し、入居時に管理リストを作成しておくことです。
衣類や日用品にフルネームで記名しておけば、誤配や紛失時の確認がスムーズになります。また、記入内容を記録し、定期的に見直すことで、情報の更新漏れを防げます。
記名と管理リストの徹底は、シンプルながら効果の高い予防策です。
洗濯・清掃時のチェック体制強化
洗濯や清掃中に私物が移動・廃棄されることも、紛失の一因です。
とくに衣類や日用品は混ざりやすく、確認不足で他の居室に届けてしまうケースもあります。
作業前後の持ち物チェックをルール化し、ダブルチェックなどで確認体制を強化することで、誤配や廃棄ミスの防止につなげましょう。
定期的な居室内の私物点検と記録の保存
私物の点検を月1回などでルール化し、保管場所や状態を記録しておくことで、紛失や盗難への早期対応が可能になります。
通帳や補聴器など高価な物は、家族と情報を共有しておくと安心です。
日常的な記録の積み重ねが、トラブル防止と信頼確保になります。
防犯カメラを設置すれば、記録を残す手間が省けます。導入を検討する場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
老人ホームに防犯カメラを導入すべき理由
物の紛失や盗難が起きたとき、「誰が・いつ・どこで」関わったのかを正確に把握するのは難しいものです。
こうした状況に備えて、防犯カメラを設置すると、リスクを軽減できます。
記録が残ることによって、誤解や不信感を防ぎ、職員と家族双方の安心につながる点が大きな利点です。
ここでは、防犯カメラの導入によって得られる具体的な効果を3つ紹介します。
防犯カメラのメリット3つ
- トラブルを未然に防ぎ、職員を守る
- ご家族への安心感と信頼が向上する
- トラブル発生時の重要な証拠になる
それぞれのメリットを詳しく見ていきましょう。
トラブルを未然に防ぎ、職員を守る

防犯カメラの最大の効果の1つは、施設内のトラブルそのものを未然に防ぐ「抑止力」です。
カメラの存在により、入居者・職員ともに意識が変わり、注意深く行動するようになります。
とくに職員にとっては、無実であっても「盗んだのでは」と疑われるリスクから自分を守る手段になります。
防犯カメラによる職員保護の効果は以下のとおりです。
- 根拠のない疑いから自分を守れる
- 証拠があることで説明責任を果たせる
- 管理責任の所在を明確にできる
トラブルの芽を摘み、職員の安心を守るためにも、防犯カメラの導入は有効です。
ご家族への安心感と信頼が向上する

介護施設で起きたトラブルに対し、家族が気にするのは「本当に適切な対応がされているのか」という不透明さです。
防犯カメラを設置することで、その不安を払拭できます。映像が残っていれば、「言った・言わない」ではなく、事実に基づいた説明が可能となるためです。
とくに入居直後や、トラブルが続いた時期には、カメラがあること自体が安心材料になります。大切な家族を預ける立場として、見守りの可視化は大きな信頼につながるでしょう。
防犯カメラ設置による家族側のメリットは以下のとおりです。
- 映像で記録されるため安心できる
- 職員の接し方や対応の様子が見える
- 証拠があるので説明に納得しやすい
カメラがあることで「見守られている」という安心感が入居者・家族に共有されます。
トラブル発生時の重要な証拠になる
万が一、紛失や盗難などのトラブルが発生した場合、防犯カメラの映像は明確な証拠となるのが、導入するメリットです。
証言だけでは食い違いや誤解が生じやすく、対応が長期化する原因になりますが、映像があれば客観的に状況を判断できます。
とくに責任の所在が不明確なケースでは、職員を守るだけでなく、施設としての正当性を家族や外部に説明する際にも有効です。
以下は、防犯カメラ映像が証拠として機能する場面の一例です。
| 発生した問題 | カメラ映像が果たす役割 |
|---|---|
| 所有物の紛失 | 最後に所持していた人物を確認できる |
| 職員への疑い | 対応状況を映像で確認・証明できる |
| 家族からのクレーム | 事実と異なる指摘への反証になる |
防犯カメラによる記録があるだけで、施設全体の対応力と信頼性が格段に向上します。
導入を検討している場合は、まずはご相談ください。現地調査、お見積もりの提出は無料で行います。
介護施設におすすめの高性能カメラ2選
ここでは、老人ホームで物がなくなるトラブルを防ぐ際に最適な、以下2つの高性能カメラを紹介いたします。
おすすめの高性能カメラ
- 400万画素赤外線カメラ 「TR-351VQ」
- 500万画素ドーム型IPカメラ「TR-IP9510」
それぞれ、詳しく解説するので、導入する際の参考にしてみてください。
400万画素赤外線カメラ 「TR-351VQ」
「物がなくなった」「誰かに取られたかも」といった声が入居者や家族から上がると、施設全体に不信感が生まれます。
そんなトラブルを未然に防ぎ、客観的に事実を残すために有効なのが、トリニティーの防犯カメラ「TR-351VQ」です。
夜間や屋外でも鮮明に記録できるため、施設の出入口や搬入口など物が動く瞬間を確実に捉えます。
また、いたずらや持ち出し行為の抑止にも役立つのも特徴です。
このカメラを導入すると以下のようなメリットがあります。
TR-351VQのメリット
- 赤外線付きで24時間監視、「見られている」意識で行動が慎重になる
- 鮮明な映像で事実確認ができるため、感情的な対立を防げる
- 高解像度の映像記録により、最後に物を扱った人物や時間帯を明確に特定できる
入居者・職員・家族の三者にとって「安心できる環境」をつくる1台です。
500万画素ドーム型IPカメラ「TR-IP9510」
「職員が触ったのでは?」「入居者が勝手に持ち出したのでは?」
そんな疑問の声があがるたびに、施設内の空気が重くなることはありませんか?
防犯カメラ「TR-IP9510」を導入すれば、室内の様子を映像と音声で記録でき、事実を残せます。
AIによる侵入検知やマイク機能付きで、紛失が疑われる瞬間や関係者の発言まで把握できるのが特徴です。
このカメラを導入すると以下のようなメリットがあります。
TR-IP9510のメリット
- AIによる侵入検知機能で、怪しい動きやエリアへの侵入を自動でスマホ・タブレット・PCへ通知
- 映像と音声の記録により、証言だけに頼らず正確な状況を把握できる
- 高精細500万画素の映像で、小さな物の扱いまでしっかり確認できる
「人を疑わなくて済む空間」をつくり、家族からの信頼と職員の安心感を守ります。
防犯カメラは初期費用0円のレンタルがおすすめ
「防犯カメラを導入したいけれど、コスト面が不安で踏み切れない」
そんなお悩みをお持ちの老人ホームや介護施設の皆さまへ、弊社では初期費用0円で始められる月額レンタルプランをご提案しています。
レンタルのメリット
- 初期費用0円ですぐ導入可能
- 月額固定料金でコスト管理がラク
- 機器修理・消耗品交換の永久保証つき
- 設置から保守・トラブル対応まで丸ごとお任せ
「コストを抑えながらも、安心してトラブル対策を行いたい」
そんな施設運営者様にぴったりのサービスです。どうぞお気軽にご相談ください。
まとめ:老人ホームの「物がなくなる」問題を防犯カメラで対策しよう
入居者の物がなくなったとき、「本当に盗まれたのか?」「職員が関与していないか?」といった疑いが生じると、施設の信頼は一気に揺らぎます。
こうした問題に対し、防犯カメラを設置すれば、誰が・いつ・どこで物を扱ったかを記録でき、証拠になります。
言い分の食い違いによるトラブルも減り、職員の精神的負担を軽くする効果も期待できるでしょう。
とくに、音声記録やAIによる侵入検知といった機能を持つカメラを導入すると、監視ではなく「見守り」として活用でき、家族の安心感にもつながるのがメリットです。
もし、老人ホームで物品の紛失や責任トラブルに悩んでいるのであれば、防犯カメラセンターを運営する株式会社トリニティーにぜひご相談ください。
現地調査・ヒアリングは無料で対応しており、施設に合ったカメラや設置プランをご提案いたします。