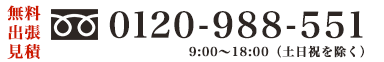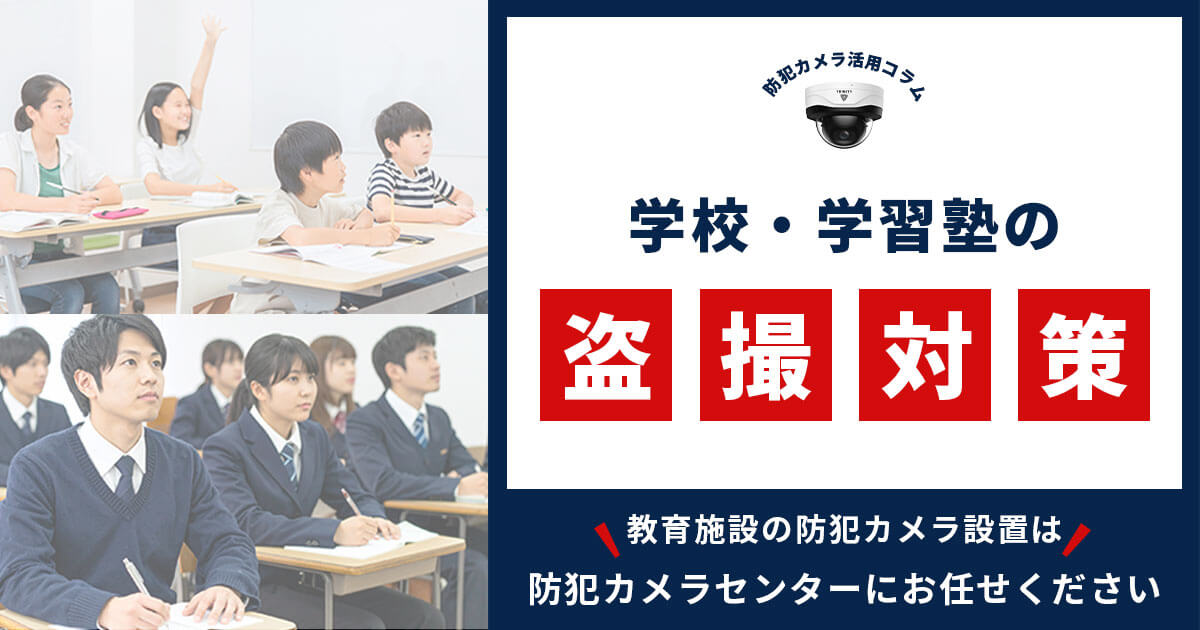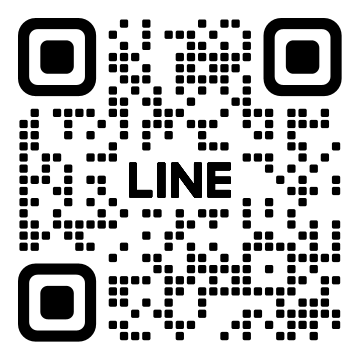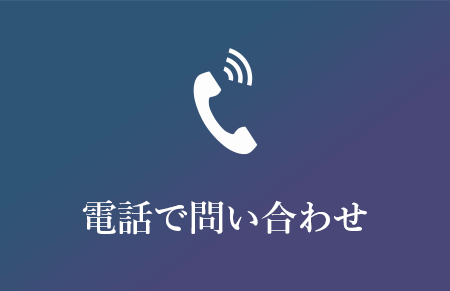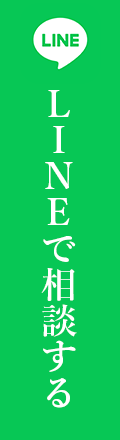すぐ始められる盗撮対策!学校内・学習塾での盗撮を防ぐ方法
学校や学習塾は、生徒が安心して学ぶための場所であるべきです。
しかし近年、教師や講師による盗撮事件、生徒同士の盗撮とSNS拡散、さらには塾のトイレや更衣室での隠しカメラなど、教育現場における盗撮トラブルが相次いで報道されています。
「気持ち悪い」「怖い」という被害者の声が示すように、盗撮は心に深刻な傷を残す犯罪です。
しかも証言だけでは証拠不十分となり、解決に至らないケースも少なくありません。
そこで本記事では、学校や塾で実際に起きている盗撮事件の事例や原因を解説するとともに、被害者へのケア、そして 防犯カメラを活用した効果的な盗撮対策を紹介します。
この記事でわかること
- 学校・塾で発生している盗撮事件の実態
- 盗撮が起きる原因と背景
- 被害者が受ける心理的ダメージと必要なケア
- 学校・塾で取り入れるべき盗撮対策チェックリスト
- 防犯カメラの効果と導入時の注意点
「盗撮の不安をなくし、生徒が安心して学べる環境を守りたい」と考えている学校関係者・塾経営者の方は、ぜひ参考にしてください。
学校・学習塾で急増する盗撮事件の実態
学校や学習塾では「盗撮なんて無縁」と思われがちですが、実際には教員や講師、生徒同士などによる盗撮事件が全国で報道されています。
安全であるべき学びの場が、盗撮によって大きな不安にさらされているのが現状です。
この章では、実際にどのような盗撮事件が起きているのかを整理して紹介します。
ここで解説すること
- 教員・講師による盗撮事件と逮捕例
- 生徒同士の盗撮とSNS拡散
- 学習塾トイレや更衣室での隠しカメラ事例
教員・講師による盗撮事件と逮捕例
学校・塾の現場で、教員・講師自身が盗撮行為を行い逮捕された事例は近年、社会的注目を集めています。
以下で代表的な事例を取り上げるので、問題の構図と傾向を見ていきましょう。
教員グループ盗撮画像共有事件(2025年発覚)
複数の教員が児童の下着やスカート内を盗撮し、SNS上のチャットグループで画像・動画を共有していた疑いで逮捕・起訴されました。
名古屋・横浜など複数地域の教員が関与しており、捜査体制が大規模に組まれた事件です。
この事件は、グループでの共有という側面があり、単独犯ではなく複数教員とのネットワークが浮き彫りになっています。
このように教員や講師による盗撮は単発の出来事ではなく、教育現場全体で起きている深刻な問題です。
生徒同士の盗撮とSNS拡散

近年は、生徒同士による盗撮がいたずら感覚で行われ、それがSNSで拡散して大きな被害につながる事件も起きています。
実際に東京都内の中学校では、男子生徒が女子生徒のスカート内をスマホで盗撮し、その動画をSNSに投稿したことで問題が発覚しました。
拡散によって被害者や保護者が強い不安を訴え、学校にも苦情が寄せられています。
参考:日テレニュース「学校内で相次ぐ“子ども同士の盗撮” 子どもが加害者にも被害者にもなる可能性…対応は?」
生徒同士の行為であっても深刻なデジタル性暴力になり得ることを理解する必要があります。
学習塾トイレや更衣室での隠しカメラ事例

学習塾という教育空間でも、トイレや更衣室に小型カメラを仕掛け、被害者のプライベートな姿を撮影するという許しがたい事件が実際に起きています。
こうした場所は見られない前提があるため、被害が露見しにくいです。
たとえば、岐阜県大垣市では、塾の個室トイレに小型カメラを設置し、10代の生徒複数を盗撮した疑いで塾の経営者が逮捕された事件が報じられました。
被害者は女子生徒で、これらの撮影は性的姿態撮影等処罰法違反などの疑いに問われています。
参考:ぎふチャン「少女3人を塾のトイレで盗撮、児童ポルノ製造疑い 岐阜県大垣市の塾経営47歳男を逮捕」
学習塾や学校施設において、プライバシーが侵されやすい場所での盗撮リスクは無視できず、管理者・運営者の警戒と対策が不可欠です。
盗撮が起きる原因と背景
学校や塾で盗撮が起きるのは、たまたまではありません。背景を知ることで、効果的な対策につなげられます。
ここで解説すること
- スマホ・小型カメラの普及
- 点検不足や管理体制の甘さ
- 教師・塾講師のモラルリスク
スマホ・小型カメラの普及

盗撮が身近な問題になっている背景には、スマートフォンや小型カメラの普及があります。
今では誰もが高性能なカメラを持ち歩き、さらにペン型や時計型といった目立たない小型機器もネットで安価に入手できます。
そのため特別な準備をしなくても盗撮が可能となり、犯罪のハードルが下がっているのです。
実際に報道される事件の多くはスマホを利用したものが中心で、アプリを使って画面を暗くしたまま撮影するケースもあります。
こうした環境を踏まえ、学校や塾では、誰でも簡単に盗撮できる時代という前提で対策を検討することが欠かせません。
点検不足や管理体制の甘さ

学校や塾で盗撮が起きる要因の1つが、施設の点検不足や管理体制の甘さです。
定期的な巡回や設備のチェックを怠ると、不審な機器が仕掛けられても発見が遅れてしまいます。
とくにトイレや更衣室など「死角になりやすい場所」は、日常的な監視が行き届きにくいためリスクが高いです。
過去の事件でも、点検をしない間に小型カメラが設置され、長期間にわたり盗撮が繰り返されていた事例があります。
定期点検や清掃時のチェックを徹底するだけでも、不審物を早期に見つけられる可能性は高まります。
点検の仕組みを持つかどうかが、盗撮防止の分かれ道になるのです。
教師・塾講師のモラルリスク

教育現場での盗撮事件では、加害者が教師や塾講師だったケースも少なくありません。
立場上、生徒や保護者からの信頼を得やすいだけに、モラルが欠けた行為は大きな裏切りです。
背景には、監督する立場にある人へのチェック体制が弱いことや、教育者だから大丈夫という過信があります。
実際に報道では、授業中に盗撮を行ったり、塾の施設に隠しカメラを仕掛けていた例も確認されています。
こうした事件は、組織全体の信頼を失墜させる深刻な問題です。
したがって学校や塾は、採用時の適性確認や定期的な倫理研修を行い、教職員自身のモラル意識を高める仕組みをつくることが欠かせません。
盗撮された気持ち悪い…被害者の心理的ダメージと必要なケア
盗撮の被害に遭った生徒は、気持ち悪い・怖いといった強い嫌悪感や不安を抱きます。
学校や保護者は、被害を受けた子どもに寄り添い、適切なケアを行うことが必要です。
この章では、被害者の心理的影響と支援の方法を解説します。
ここで解説すること
- 被害者の声と「気持ち悪い」という感情への対応
- 日常生活・学習への影響
- 学校や保護者ができる心のケア
被害者の声と「気持ち悪い」という感情への対応

盗撮の被害者が抱く「気持ち悪い」「怖い」という感情には、その心理に寄り添うことが重要です。
盗撮は身体を直接傷つけなくても、プライバシーを侵害され、強い屈辱や不安を与えます。
実際の声としては、「自分の知らないところで見られたと思うと吐き気がする」「学校に行きたくなくなった」などがあります。
こうした感情に対応するには、まず否定せずに受け止める姿勢が必要です。
サポートする際は、以下のポイントに注意しましょう。
- 「気持ち悪い」という感覚を無理に否定しない
- 安心できる環境で話を聞く
- 学校や保護者が一緒に対応方法を考える
感情の受け止め方がケアの際に意識するポイントです。共感と理解を示すことが、心の回復につながります。
日常生活・学習への影響
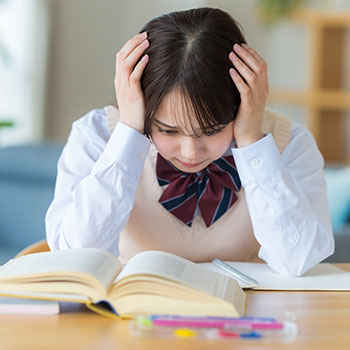
盗撮被害は、生徒の日常生活や学習に深刻な影響を与えます。
また盗撮されるのではという恐怖心から、人前に出るのを避けたり学校に通えなくなったりするためです。
集中力や意欲が低下すれば、学業成績や進学にも関わってくる可能性があります。被害を受けた生徒が抱えやすい影響は次のようなものです。
- 外出や登校に強い不安を感じる
- 授業や勉強に集中できない
- 友人や教師との関係を避けがちになる
- 将来に対する自己肯定感の低下
生徒が盗撮被害に遭った場合、学校や保護者は、生活や学習の支援まで視野に入れた対応を取る必要があります。
学校や保護者ができる心のケア

盗撮の被害を受けた生徒を守るには、学校と保護者が協力して心のケアが必要です。
実際に必要とされるケアには以下のようなものがあります。
- まず気持ちを受け止め、否定しない
- 保護者・教師が一緒に行動し、孤立させない
- 必要に応じてスクールカウンセラーや専門機関につなぐ
- 学習や生活リズムを調整し、安心できる環境を整える
学校と家庭が協力して支えれば、被害からの回復を早められます。
盗撮対策の基本!学校と塾が取るべき実践チェックリスト
盗撮を未然に防ぐには、日常の中でできる対策を具体的に取り入れることが重要です。
学校や塾は「事件が起きてから対応する」のではなく、日頃から仕組みやルールを整えておくことで、被害の発生を減らせます。
この章では、教育現場で実践できる基本的な盗撮対策をチェックリスト形式で紹介します。
ここで解説すること
- 定期点検・巡回で「隠しカメラ」を防ぐ
- 教職員・講師のスマホ利用ルールの徹底
- 防犯教育・生徒への啓発
定期点検・巡回で「隠しカメラ」を防ぐ

盗撮を防ぐには、施設内の定期点検や巡回を行い、不審な機器の早期発見に努めましょう。
トイレや更衣室などは死角が多く、隠しカメラを設置されやすい場所です。
日常的な確認を怠ると、長期間にわたり被害が続く恐れがあります。
実際に、学習塾のトイレで小型カメラが設置されていた事件では、発見が遅れたことで被害が拡大しました。
盗撮を防ぐために学校や塾ができる工夫は以下の通りです。
- 清掃時に不審物や改造の有無を確認
- 設備や什器の裏・天井・照明を定期的に点検
- 巡回を複数人で行い、チェックを習慣化する
日常点検の仕組みを取り入れて、盗撮防止につなげましょう。
教職員・講師のスマホ利用ルールの徹底

学校や塾では、教職員や講師のスマホ利用に明確なルールを設け、徹底することが盗撮防止につながります。
授業や業務中に私物スマホを自由に扱える環境では、不正利用が発生しても気づきにくくなるためです。
対策としては、次のようなルールが挙げられます。
- 授業中は職員のスマホをロッカーで一括管理
- 校務用と私物を分け、業務利用は校務用に限定
- 不審な操作や撮影行為を見かけたら報告する体制
盗撮を防ぐには教職員や講師のスマホ管理が必要です。
明確なルールがあることで、生徒・保護者の安心感も高まります。
防犯教育・生徒への啓発

盗撮を防ぐには、学校や塾が生徒自身に防犯意識を持たせる教育も必要です。
管理者だけが対策しても限界があります。
生徒が「おかしい」と気づき、行動できることで早期発見や被害防止につながります。
- 不審なスマホやカメラを見かけたら先生に伝える
- 更衣やトイレ利用時に違和感を覚えたらすぐ報告する
- SNSでの写真や動画の取り扱いリスクを学ぶ授業を行う
生徒自身が自分を守る行動を理解することが、学校全体の防犯力を高める大切な要素です。また、教育により生徒同士の盗撮も防げます。
防犯カメラによる盗撮対策の効果と注意点
学校や塾では、防犯カメラの設置が盗撮対策として有効です。
抑止力や証拠確保の面で役立ちますが、同時にプライバシーへの配慮や管理方法も重要になります。
導入する際は、効果と注意点の両方を理解することが大切です。
この章では、防犯カメラによる盗撮対策について次の観点から解説します。
ここで解説すること
- 防犯カメラは盗撮を抑止できる
- トラブル時の証拠になる
- 映像管理の注意点
- 設置場所の工夫
防犯カメラは盗撮を抑止できる

防犯カメラの最大の効果は、盗撮を未然に防ぐ抑止力です。
人は監視されていると感じるだけで不正行為を控える傾向があります。
とくに盗撮は人目を避けて行われるため、防犯カメラの存在が大きな心理的ブレーキになります。
教育現場での活用ポイントは以下のとおりです。
- 校舎入口や廊下など共用スペースに設置する
- カメラ設置を掲示し、抑止力を高める
- 死角を減らすレイアウトで設置する
このように防犯カメラは、事件が起きてから証拠を残すだけでなく、起きないようにする効果が期待できるのです。
トラブル時の証拠になる
防犯カメラは、盗撮などのトラブル発生時に証拠として役立ちます。
被害者の証言だけでは状況を証明しにくい場合でも、映像記録があれば加害者の特定や行為の確認ができるのが防犯カメラの強みです。
防犯カメラ映像が証拠として活用できる場面は次のとおりです。
- 盗撮行為があった時間や場所の特定
- 不審な人物の動線の記録
- 学校や塾が「安全対策を行っていた」と示す証拠
防犯カメラは、事件後に責任を明確にする重要な証拠にもなります。
映像管理の注意点
防犯カメラを設置する際は、映像の管理方法に十分注意しなければなりません。
映像データはプライバシーに直結するため、扱いを誤ると「二次被害」や「不信感」につながります。
保護者や生徒から安心して理解を得るには、透明性のあるルール作りが欠かせません。
安全に運用するためのポイントは次のとおりです。
- 映像はパスワード管理し、閲覧権限を限定する
- 保存期間を明確に決め、不要な映像は削除する
- 保護者や職員に「何のために設置しているか」を説明する
防犯カメラは、どう管理するかも信頼を左右します。盗撮対策に使う際は、慎重に行いましょう。
設置場所の工夫
防犯カメラで盗撮対策を行う場合、プライバシーにも配慮した設置場所の選定が必要です。
被害の可能性があるからといって、トイレや更衣室などに直接設置してしまうとプライバシーを侵害してしまいます。
そのため「盗撮が行われやすい周辺」を見守る配置が大切です。
利用者に不快感を与えず、効果的に監視できる場所を選ぶことが求められます。
- トイレや更衣室の出入口を映す
- 廊下や階段など共用スペースを重点的に監視
- 死角ができないように複数台でカバー
- カメラ設置を掲示して抑止効果を高める
防犯カメラは設置場所を正しく選ぶと、安心感とプライバシーを守って盗撮対策ができます。
盗撮事件が起きたときの対応と法的責任
万が一、学校や塾で盗撮事件が発生した場合は、迅速な対応が必要です。
被害者の心理的ダメージが深まるだけでなく、学校や塾が安全配慮を怠ったとして責任を問われる可能性もあります。
事件を軽視せず、法的な観点も含めて正しく行動することが重要です。
この章では、盗撮事件発生時の対応と責任について整理します。
ここで解説すること
- 盗撮はどのような罪にあたる?
- 学校や塾が問われる法的責任
- 被害生徒の支援と相談ルート
盗撮はどのような罪にあたる?
盗撮は法律で処罰されるれっきとした犯罪です。
2023年に「性的姿態撮影等処罰法(撮影罪)」が施行され、盗撮は全国一律で刑事罰の対象となりました。
従来の迷惑防止条例に比べ、法的根拠が明確になり罰則も強化されています。
盗撮に関係する代表的な法律は以下のとおりです。
- 性的姿態撮影等処罰法(撮影罪)
- 正当な理由なく、下着や胸部などの性的な姿態を撮影すると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金。
参考:法令検索e-Gov「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」 - 住居侵入罪(刑法130条)
- 許可なく学校や塾の施設に侵入し盗撮した場合に適用。3年以下の懲役または10万円以下の罰金。
参考: 法令検索e-Gov「刑法 第130条(住居侵入等)」 - 児童ポルノ禁止法
- 18歳未満の児童を対象にした盗撮映像を所持・保存・流通した場合に適用。懲役刑や罰金刑が科される可能性あり。
参考: 法令検索e-Gov「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」
盗撮は明確な犯罪であり、厳しい刑罰が科される可能性があります。教育現場でも「違法行為である」と周知することが重要です。
学校や塾が問われる法的責任
盗撮事件が学校や塾で発生した場合、加害者本人だけでなく、運営側も「法的責任」を問われる可能性があります。
教育機関には安全配慮義務があり、生徒が安心して学べる環境を整える責任があるためです。
点検や管理を怠った結果、被害が発生すれば、過失があったとみなされることがあります。
学校や塾に求められる主な法的責任は次のとおりです。
- 安全配慮義務違反
- 施設管理や職員の監督不足で被害が発生した場合、損害賠償請求の対象になり得る。
- 使用者責任(民法715条)
- 教職員や講師の不法行為に対して、雇用者である学校法人や塾運営会社が責任を負う場合がある。
盗撮は個人の問題ではありません。学校や塾は組織として安全体制を整える義務があります。
被害生徒の支援と相談ルート
盗撮被害を受けた生徒には、早期に適切な支援と相談ルートを示すことが不可欠です。
心理的ショックや不安を一人で抱え込むと、長期的な心の傷や不登校につながる恐れがあります。
信頼できる相談窓口を案内し、安心して支援を受けられる環境を整えることが大切です。
- 学校内のスクールカウンセラーや養護教諭
- 保護者や信頼できる先生との連携
- 警察(少年相談窓口や生活安全課)
- 外部の専門機関(法テラス、児童相談所、性犯罪被害者ワンストップ支援センター)
「誰に相談していいかわからない」という孤立を防ぐことが、被害生徒を守る第一歩です。
学校・家庭・専門機関が連携して支援する体制づくりが求められます。
「うちの学校(学習塾)は大丈夫」ではなく、何かあったときのために盗撮対策を進めてみてください。
学校や学習塾の運営はもちろん、生徒や教師、保護者が安心して生活を送れるようになります。
学校・塾の防犯カメラはレンタルがオトク!
「防犯カメラを設置したいけれど、費用がかかりそう…」
そんな方におすすめなのがレンタルプランです。
購入に比べて初期費用を大幅に抑えられるだけでなく、専門スタッフが設置からサポートまで対応するので安心です。
レンタルを選ぶメリット
- 初期費用0円で導入しやすい
- 毎月の定額料金でわかりやすい
- 設置から修理・メンテナンスまでおまかせ
無料の現地調査を行い、環境に合わせた最適なプランをご案内します。
学校や塾など、教育施設での防犯カメラ導入をご検討の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
よくある質問
最後に学校・学習塾の盗撮対策についてよくある質問を紹介します。
学校で盗撮されたらどうすればいい?
まず信頼できる先生や保護者にすぐ伝えましょう。
そのうえで学校と連携して警察へ相談することが大切です。
証拠となる映像や不審物は自分で触らず、専門機関に対応を任せてください。
早期に行動することで被害の拡大を防げます。
防犯カメラを設置するとプライバシー侵害になりますか?
適切な場所に設置し、利用目的を説明すれば原則としてプライバシー侵害にはなりません。
ただしトイレや更衣室などは絶対にNGです。
映像管理のルールを明確にし、保護者や生徒に周知することが安心につながります。
盗撮は何歳から捕まりますか?
盗撮は年齢に関係なく犯罪です。
刑事責任を問われるのは14歳以上からで、実際に中高生が逮捕された例もあります。
14歳未満でも児童相談所に通告されるなど、厳しく指導される可能性があります。
まとめ 盗撮対策で学校・塾に安心を
学校や学習塾で起こる盗撮は、「気持ち悪い」「怖い」という被害者の声が示すように深刻な心理的ダメージを与えます。
しかも目撃者がいない場合、証言だけでは証拠が不十分となり、解決に至らないケースもあります。
そこで有効なのが、防犯カメラによる対策です。
- 防犯カメラによって盗撮を抑制できる
- 盗撮発覚時に証拠を残せる
- 保護者や生徒に安心感を与えられる
学校や学習塾で発生する盗撮対策は、今や必須の時代となりました。
関係者に説明を行い、理解してもらう必要はありますが、防犯カメラの設置は必要不可欠です。
盗撮のニュースを見て、危機感を覚えた方はぜひ一度お問い合わせください。
教育施設のお客様向け 防犯カメラ特設ページ

保育園や学校などの教育施設では、安全な環境づくりが重要です。
不審者の侵入や事故を防ぐためには、防犯カメラなどのセキュリティ対策が求められています
施設の安全性向上をお考えの方は、下記の特設ページで対策のポイントをご確認ください。
詳細はこちら